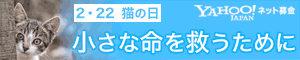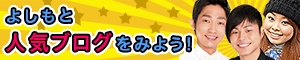偉人の名言集【114】■ 松崎 俊道 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34331803.html経営者、経営コンサルタント、自己啓発作家。 ミッションは、「元気なリーダー育成を通して、元気な社会づくりに貢献する」。 人づくり歴30年、直接育てたリーダーは3,000人を越える。 社団法人日本能率協会、株式会社船井総合研究所を経て、 1988年に株式会社「組織デザイン」を設立。 通信自己啓発システム「カイゼン・オンライン」を主宰している。 主な著書に 「リ-ダ-へ贈る詩迷えども、歩き続けるあなたへ」 「元気力 あなたの心を切換える101のスイッチ」 「元気が出てくる心の詩(うた)」 「仕事をおもしろくする5ステップ! 「あなたにしかできないコト」がきっとある!」 などがある。 抽象的に困っている人は、前に進まない。
ボンヤリとした困り方だから。 具体的に困っている人は前に進む。 ハッキリとした困り方だから。 売上が上がらない…ではなくて、 A商品が20%降下した…というように 職場が暗い…ではなくて Aさんとのコミニュケーションが少ない…というように。 具体的に困ってごらん。 具体的に動けるから。 ■ 土屋 耕一 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34329915.html コピーライター、回文作家、随筆家。 23歳の時に、知り合いからTBSラジオのモニター募集に採用され、 朝日新聞に匿名で批評を書くなどの仕事を経て、ラジオの企画立案者募集の広告を見て、応募。 のちに資生堂の宣伝文化部を紹介され、1956年に嘱託社員として入社。 デザイナーならびにイラストレーターをしていた山名文夫・水野卓史などのデザイナーのもとで、 コピーライターとしての研鑽を積んでゆく。 資生堂を経て、1960年に日本初の広告制作プロダクションとして設立された ライトパブリシティへ入社、当時の主要アートディレクターならびに デザイナーとして知られる大橋正や和田誠、向秀男らと組んで、 明治製菓やキッコーマン、伊勢丹、東レなどの企業広告のコピーを書いてゆく。 また長年に渡り、伊藤園から発売されている「おーいお茶」のパッケージに 記載されている季節の川柳選者としても、その名を知られた。 一人より十人の方が強いのは綱引きである。
発想とは、一人の頭が、十人よりも強い力を出す技術を言う。 ■ 佐々木 常夫 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34328006.html 1944 年秋田市生まれ。 6歳で父を亡くし、4人兄弟の次男として母の手ひとつで育つ。 1969 年東大経済学部卒業、同年東レ入社 自閉症の長男に続き、年子の次男、年子の長女が誕生 しばしば問題を起こす長男の世話、加えて、肝臓病とうつ病に罹った妻が43回もの入院と 3度の自殺未遂を起こす。 会社では大阪・東京と6度の転勤、破綻会社の再建やさまざまな事業改革など多忙を極め それに対して全力で取り組む生活。 2001年、東レ同期トップで取締役となり、 2003年より東レ経営研究所社長となる。 何度かの事業改革の実行や3代の社長に仕えた経験から独特の経営観をもち、 現在経営者育成のプログラムの講師などを実践している。 社外業務としては内閣府の男女共同参画会議議員などの公職も務める。 「目の前の仕事」に真剣になりなさい。
きっと、見えてくるものがある。 ■ 行徳 哲男 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34325761.html 1933年福岡生まれ。成蹊大卒。 労働運動激しき時代、衝撃的な労使紛争を 体験し、“人間とは何か”の求道に開眼。
69年渡米、Tグループの世界と出会い、
米国流の行動科学・感受性訓練と、日本の禅や経営哲学を融合させ、BE訓練(Basic Encounter Training=「人間開発・感性のダイナミズム」)を完成させる。 一番素敵なものは当たり前の中にある。
そのことが分かった人間は奮い立っていく。 ■ 鳥羽 博道 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34323695.html 埼玉県深谷市生まれの日本の実業家。 ドトールコーヒー創設者、名誉会長。 高校中退後、レストラン、コーヒー豆焙煎卸営業会社勤務を経てブラジルへ渡航。 3年間現地のコーヒー農場で汗を流し、帰国後にドトール・コーヒーを設立。 同社を東証一部上場企業へと育て上げた経営者。 ニュービジネス協議会(NBC)の副会長なども務め、次世代の起業家育成に尽力している。 徳川家康の 「 願いが正しければ、時至れば必ず成就する 」 という言葉は
私の座右の銘のひとつになっている。 正しい願い、ポリシーというものは時期が来れば必ず成就する。 その努力と忍耐は必ず報われるものだと思う。 ■ 池井戸 潤 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34321422.html 小説家。岐阜県出身。 慶應義塾大学卒。 1998年、銀行の暗部に迫った小説『果つる底なき』で 第44回江戸川乱歩賞を受賞(同時受賞は福井晴敏の「Twelve Y. O.」)。 2010年、談合の是非を問うた小説『鉄の骨』で第31回吉川英治文学新人賞を受賞。 この『鉄の骨』(NHKにてドラマ化。 主演・小池徹平)と自動車会社の傲慢を暴く代表作『空飛ぶタイヤ』(WOWOWにてドラマ化。 主演・仲村トオル)は、直木賞候補にもなった。 2011年、日本の下町工場技術や職人魂を描いた『下町ロケット』で第145回直木賞受賞。 同作は同年8月よりWOWOW「ドラマW」(主演・三上博史)の枠にて放映された(2012年1月DVD化)。 小さなことでもいいから
まず何か1つ変えてみる。 必ずそこに突破口があります。 ■ 西郷 隆盛 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34318777.html 武士(薩摩藩士)、軍人、政治家。 薩摩藩の盟友、大久保利通や長州藩の木戸孝允(桂小五郎)と並び、「維新の三傑」と称される。 維新の十傑の1人でもある。 位階は正三位。 功により、継嗣の寅太郎に侯爵を賜る。 急速は事を破り、寧耐(ねいたい)は事を成す。
-note- 西郷隆盛大成する人生について語った西郷隆盛の名言。 「物事はあわてて取り組むと失敗するが丁寧に進めれば成功する」という意味。 江戸城の無血開城を実現した「明治の巨人」に心服した旧庄内藩士らが、 西郷から直接聞いた教えをまとめた「南洲翁遺訓」に収録されている言葉。 ■ 杉田 満裕 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34317285.html 作家。 会社勤めのかたわら執筆活動を行っている人物であり、 新聞や雑誌に連載を持つほか、講演活動なども行っている。 主な著書に 「“運のいい人”になる12週間の小さな心がけ」 「少しずつ元気を取り戻すヒント うつ、落ち込みから立ち直るきっかけの作り方」 「少しずつ毎日を充実させるヒント 幸せ、夢、成功への「あと一歩」の踏み出し方」 「少しずつ自分を強くするヒント 幸せ、夢、成功を引き寄せる考え方」などがある。 あなたが「十分後にどんな行為をするか」については、
いまから計画できるし、実行に移せるということである。 十分後の未来なら、自分の意志で変えることができる。 そして、十分後の未来は、無限の未来でもある。 ■ 玉木 文之進 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34315431.html 幕末の長州藩士で教育者・山鹿流の兵学者。 松下村塾の創立者。吉田松陰の叔父に当たる。 天保13年(1842年)に松下村塾を開いて、幼少期の松蔭を厳しく教育した。 また乃木希典も玉木の教育を受けている。 痒み(かゆみ)は私。
掻くことは私の満足。 それをゆるせば長じて人の世に出たとき私利私欲をはかる人間になる。 だからなぐるのだ。 -note- 玉木 文之進は、幼少期の「吉田松陰」の教育者として知られる。 司馬遼太郎氏によれば、玉木文之進は「侍とは、公に尽くすものである。」という信条を、 まだ幼い吉田松陰に叩き込んだ。 ある夏の日、燃えるような夏草のあぜ道で、書物を読んでいた松陰が うるさくたかる蠅のかゆみに思わず掻いた。 玉木文之進が跳びあがって松陰を死ぬほどなぐりつけた。 学問を学ぶ事は公につくす自分を作る為であり、 読書中に頬を掻くのは私情である。 この「公私」の意識的な分離という精神作用が「身体は私、心は公」(士規七則) という思想に高まっていく事になったそうです。 「世に棲む日日」参照。 ■ 村上 一男 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34313437.html 長崎県出身のカイロドクター(カイロプラクティック師)、教育者。 学校法人村上学園理事や全国カイロプラクティック師会会長、 カイロプラクティツク振興協同組合理事長などを務める人物。 日本柔道整復専門学校を経て渡米し、パーマーカイロプラクティック大学で技術を磨く。 帰国後、千葉県柏市にK-Mカイロプラクティック研究所を設立し、村上腰痛センターを全国展開。 その後、村上整体専門医学院東京カイロプラクティックカレッジを設立し、 カイロプラクティック師の教育にも力を注ぐ。 「 なかなか結果が出ない 」
と言って悩んでる人もたくさんいます。 彼らの問題点はどこにあると思いますか。 答えはすごく簡単。 頑張っていないからです。 ■ 養老 孟司 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34310960.html
解剖学者。 東京大学名誉教授。専門は解剖学。 文化や伝統、社会制度、言語、意識、心など人のあらゆる営みは 脳という器官の構造に対応しているという「唯脳論」を提唱した。 この論は、『現代思想』(青土社)の連載をもとに出版された 『唯脳論』(青土社)にまとめられている。 やることがないとか面白くないとか言っていませんか?
世の中が面白くないですか? でも世の中簡単に変わらないですよ。 じゃあ、どうすれば面白くなるのか。 自分が変わることです。 自分が変われば世の中が面白くなる。 |
この記事に