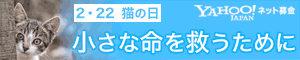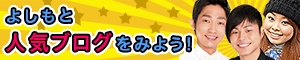偉人の名言集【124】■ 徳富 蘇峰 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34562842.html明治・大正・昭和の3つの時代にわたる日本のジャーナリスト、思想家、歴史家、評論家。 また、政治家としても活躍して、戦前・戦中・戦後の日本に大きな影響をあたえた。 人生の要は七分の常識に
三分の冒険心を調合するを以て、 適当なりとなすべし。 ■ 小泉 清子 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34560449.html 実業家であり、きもの研究家である。 呉服販売会社「鈴乃屋」代表取締役会長。 東京府立第一高等女学校を卒業後、当時の内務省に勤務。 その後結婚し子供を2人もうけるが、夫は太平洋戦争(大東亜戦争)で戦死した。 日本の敗戦後の1947年(昭和22年)、子供を養うため、生地に近い上野で呉服店「鈴乃屋」を開業。 苦難の末に、会社を全国規模の呉服販売チェーンストアに成長させた。 私が思うに、どの商売でも難しく、楽な商売なんてない。
それだけに、この商売と決めたら辛抱強く、やり抜くことが大切で決して諦めてはならない。 人間、やる気さえあれば知恵も出てくるものです。 ■ 桜井 美姫 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34558685.html 東海テレビ・泉放送制作の制作の昼ドラ「毒姫とわたし」に登場する元キャバクラ嬢の車いす作家。 生まれながらに足に障害を持ち、親に捨てられ児童養護施設「天使園」で22歳まで過ごす。 大学卒業後、キャバクラで働きながらに勤務する傍ら、出版社の小説賞に作品を応募し、 きみじま文芸賞・受賞作の「海に咲くさくら」でデビューを果たす。 何事にもぶつかって、傷付いて、
ガンガン経験値を上げていくべきや! 傷付いて磨かれるからこそ あんたの魅力は輝くねん。 ■ 鍵山 秀三郎 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34557257.html 株式会社ローヤル(現 イエローハット)の創業者。 また、日本を美しくする会の相談役でもある。 掃除をテーマにした活動・講演を全国各地で行なっている。 リーダーとして一番心しなければならないのは、
「至誠 神の如し」ということに尽きるのではないかと思っています。 リーダーは誠を尽くすしかない。 ■ 岩波 茂雄 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34555256.html 出版人、岩波書店創業者。貴族院多額納税者議員。尋常小学校、高等小学校をへて、 1895年(明治28年)には諏訪実科中学校(現・諏訪清陵高)へ入学。 在学中には父が死去し、戸主となる。 母を助け農業をしていたが1899年に上京し、日本中学に入学。 母が学資を仕送りしてくれた。 ある時母親が上京すると茂雄は東京見物をさせようと思うも 母は用事が済むとさっさと帰郷してしまった。 息子を勉強させたいばかりに働いたのだという。 翌年には卒業し、1901年、杉浦重剛を慕い第一高等学校に入学する。 藤村操が自殺した際、彼の友人でもあった茂雄は哲学書等を携えて40日間山小屋に篭もり 死に付いて真剣に考え、自身も死を選びつつあったが、母親の下山の訴えでとうとう下界へ戻る。 けれど先の事件の影響を受け、落第した。 この頃、煩悶から東京本郷で求道学舎を主宰していた真宗大谷派僧侶の近角常観のもとを訪れ、 近角から著書『信仰の餘瀝』を渡される。 試験放棄のため除名中退処分となり、再起して1905年東京帝国大学哲学科選科に入学。 他より幾分でも高く買い入れ、また幾分でもこれを他より安く売る。
商売の秘訣を聞かれてもこれ以外に答えようがない。 ■ 広岡 達朗 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34553391.html 広島県呉市出身のプロ野球選手(内野手)・プロ野球監督、野球解説者(野球評論家)。 東京都町田市在住。 愛称は「ヒロさん」、あるいは単に「ヒロ」。 また、野村克也や森祇晶が「狸」と呼ばれるのに対して、 広岡は「狐」と呼ばれることもある。 指導とは根気と見つけたり。
結局、人を指導するということは、 その相手とじっくり向かい合って、 根くらべをすることなのだ。 ■ 安田 隆夫 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34551211.html 1973年(昭和48年)慶應義塾大学法学部卒業後、不動産会社に勤務したが倒産。 1978年(昭和53年)東京都杉並区に雑貨店「泥棒市場」を起業し、終夜営業が受けて成功した。 1980年に株式会社ジャスト(現・株式会社ドン・キホーテ)、 1982年に株式会社リーダーを設立。 1989年(平成元年)には第1号店となる「ドン・キホーテ」府中店を開店。 業界常識は勝利者の論理であって、勝利のための論理ではない。
だから、後発企業が先発企業のマネをしても絶対に勝てない。 ■ 小林 一三 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34549323.html 実業家。 阪急電鉄や宝塚歌劇団をはじめとする阪急東宝グループ(現・阪急阪神東宝グループ)の創業者。 鉄道を起点とした都市開発、流通事業を一体的に進め相乗効果を上げる私鉄経営モデルの原型を 独自に作り上げた。 青年よ、独立せよ。
大会社にあこがれるな。 商売はいくらでもある。 仕事はどこにでもある。 ■ 東郷 平八郎 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34547187.html
武士(薩摩藩士)、軍人である。 階級は元帥海軍大将。栄典は従一位・大勲位・功一級・侯爵。 明治時代の日本海軍の司令官として日清及び日露戦争の勝利に大きく貢献し、 日本の国際的地位を「五大国」の一員とするまでに引き上げた。 明治38年12月21日
東郷司令長官による連合艦隊解散式における訓示(草稿者:海軍参謀 秋山真之) 現代語訳 20数ヶ月にわたった戦争も、今や過去のこととなり、わが連合艦隊は、今やその任務を果して、 ここに解散することとなった。 しかし艦隊は解散しても、わが海軍軍人の務めや責任が、軽減するということはない。 この戦役で収めた成果を、永遠に保ち、さらに一層国運をさかんにするには、平時戦時の別なく、 まずもって外からの守りに対し、重要な役割を持つ海軍が、常に万全の海上戦力を保持し、 ひとたび事あるときは、ただちに、その危急に対応できる備えが必要である。 ところで、その戦力であるが、戦力なるものはただ艦船兵器等有形の物や数によってだけ、 定まるのではなく、これを活用する能力すなわち無形の実力にも実在する。 百発百中の砲は、一門よく百発一中、いうなれば百発打っても一発しか当らないような砲なら 百門と対抗することができるのであって、この理に気づくなら、われわれ軍人は無形の実力の充実、 即ち訓練に主点を置かなければならない。先般わが海軍が勝利を得たのは、 もちろん天皇陛下の霊徳によるとはいえ、一面また将兵の平素の練磨によるものであって、 それがあのような事例をもって、将来を推測するならば、たとえ戦争は終ったとはいえ、 安閑としてはおれないような気がする。 考えるに軍人の一生は戦いの連続であって、その責務は平時であれ、戦時であれ、 その時々によって軽くなったり、重くなったりするものではない。 事が起これば、戦力を発揮するし、事がないときは、戦力の蓄積につとめ、 ひたすらその本分を尽くすことにある。 過去一年半かの風波と戦い、寒暑に直面し、しばしば強敵とまみえて生死の間に出入りしたことは、 もちろんたいへんなことではあったが、考えてみると、これもまた、長期の一大演習であって、 これに参加し、多くの知識を啓発することができたのは、軍人として、 この上もない幸せであったというべきで、戦争の苦労も些細なものにしてくれるといえよう。 もし軍人が太平に安心して、目前の安楽を追うならば、兵備の外見がいかに立派であっても、 それはあたかも、砂上の楼閣のようなものでしかなく、ひとたび暴風にあえば、 たちまち崩壊してしまうであろう。まことに心すべきことである。 むかし神功皇后が三韓を征服されて後、韓国は400余年間、わが支配の下にあったけれども、 ひとたび海軍がすたれると、たちまちこれを失い、また近世に至っては、徳川幕府が太平になれ、 兵備をおこたると、数隻の米艦の扱いにも国中が苦しみ、またロシアの軍艦が千島樺太をねらっても、 これに立ち向うことができなかった。 目を転じて西洋史を見ると、19世紀の初期ナイル及びトラファルガー等に勝った英国海軍は、 祖国をゆるぎない安泰なものとしたばかりでなく、それ以後、後進が相次いで、 よくその武力を維持し、世運の進歩におくれなかったから、今日に至るまで永く国益を守り、 国威を伸張することができた。 考えるに、このような古今東西の教訓は、政治のあり方にもよるけれども、 そもそもは軍人が平安な時にあっても、戦いを忘れないで、備えを固くしているか、どうかにかかり、 それが自然にこのような結果を生んだのである。 われわれ戦後の軍人は、深くこれらの実例、教訓を省察し、これまでの練磨の上に、 戦役の体験を加え、さらに将来の進歩を図って、時勢の発展におくれないように 努めなければならない。 そして常に聖諭を泰戴して、ひたすら奮励し、万全の実力を充実して、時節の到来を待つならば、 おそらく、永遠に国家を護るという重大な責務を果たすことが出来るであろう。 神は平素ひたすら鍛錬につとめ、戦う前に既に戦勝を約束された者に、 勝利の栄冠を授けると共に、一勝に満足し、太平に安閑としている者からは、 ただちにその栄冠を取上げてしまうであろう。 昔のことわざにも「勝って兜の緒を締めよ」とある。 1905年12月21日 連合艦隊司令長官 東郷平八郎 |
この記事に