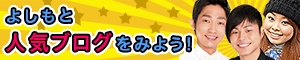■ 土門 拳 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34946385.html 昭和時代に活躍した日本の写真家。 リアリズムに立脚する報道写真、日本の著名人や庶民などのポートレートやスナップ写真、 寺院、仏像などの伝統文化財を撮影し、第二次世界大戦後の日本を代表する写真家の一人とされる。 また、日本の写真界で屈指の名文家としても知られた。 風景に向かって手も足も出ない、
そのまま撮ってくるというようなやり方では、 新しい今の風景写真は作れない。 作者自身の 日本の風土というものに対し、 民族というものに対し、 伝統というものに対して はっきりした定見をもっていかなければ撮れない。 - 雑 感 - 昨年の事ですが、あるセミナーに参加してドラッカーの マネジメントをテーマにした講話を拝聴する機会が有りました。 とても興味が出て「もしドラ」→「マネジメント」を読み、 考え方が大きく変わってしまいました。 定見とは、 「他人の意見に左右されない、その人自身の意見。」 と辞書に書いて有ります。 私が変わった事は、 花屋として 「より良いフラワーギフトを販売する事」 ではなく、 「私達は日々の人間の心を豊かにする価値創造会社でございます。」 と、なった事です。 たかが花ではなく、されど花となるべく、日々修行です。(-_-;) ■ 三国志「呉書・呂蒙伝」 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34944758.html 「三国志」とは、魏(ぎ)・呉(ご)・蜀(しょく)の三国が争覇した、 三国時代の歴史を述べた歴史書である。 男子三日会わざれば刮目して見よ。
原文:「士別れて三日なれば刮目して相待すべし。」 - 雑 感 - 私がサラリーマン時代、三国志を信奉している上司から 仕事の取り組み方や考え方を指導して頂きました。 今も私の考え方の基本になっているように思います。 今日の言葉の意味は、 「男の子は三日も会わないでいると驚くほど成長しているものだという意味で、 人の学業や仕事・人間性などがいかに向上したか、良く見なさいということ」 です。 刮目(かつもく)とは「目をこすって、よく見ること。」 三国志の時代、呉の国に呂蒙という猛将がいて、彼の名は他国にも響いていたけれど、 無学であったので主君である孫権が、勉強する事をさとしました。 それから呂蒙は兵法や歴史を学んで、勇猛さに知力をつけて後々は、 関羽をやっつけてしまうほどの武将に成長します。 同じく呉の知将である魯粛が呂蒙を尋ねて 「もう、呉の国の中の呂蒙ではない!」 と褒めたたえたという故事からきた日本の慣用句です。 私も呂蒙になったつもりで日々修行です。(-_-;) ■ 安田 理深 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34943250.html 仏教学者。真宗大谷派の僧籍を持つ。 青年時代には東洋哲学やキリスト教などを学んだが、 金子大栄の著作に触れて親鸞思想に目覚め、大谷大学へ入学。 晩年は私塾相応学舎を主宰し、浄土教教理学のほか、唯識などの講義を行った。 その学識から幾度も大学教授などの誘いがあったが、生涯無位無官を貫いた。 しなくてはならないのならやめなさい。
やらずにおれないのならやりなさい。 - 雑 感 - 私は子供の時から親に何かを強要されたりする事なく 勝手気ままに生きてきました。 いわゆる放任主義で育ってきたような感じです。 振り返ると、自分の力で解決していく力のようなものが 身についたような気もします。 義務と感じるか、それとも自らそう望むのかでは、 その結果は大きく違ってくるはず。 勉強も、趣味も、今の仕事も、 徹底的に伸ばしていきたいと思います。 日々修行です。(-_-;) ■ 坂本 龍馬 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34940721.html 江戸時代末期の志士、土佐藩郷士。 土佐郷士に生まれ、脱藩した後は志士として活動し、 貿易会社と政治組織を兼ねた亀山社中(後の海援隊)を結成した。 薩長同盟の斡旋、大政奉還の成立に尽力するなど 倒幕および明治維新に影響を与えた。 大政奉還成立の1ヶ月後に近江屋事件で暗殺された。 1891年(明治24年)4月8日、正四位を追贈される。 人として生まれたからには、
太平洋のように、 でっかい夢を持つべきだ。 - 雑 感 - 私は高知県の桂浜まで何度も旅して太平洋を細い目で見つめる龍馬さんに逢ってきました。 坂本龍馬ってどんな人だったのだろう? 「過激なること豪も無し。且つ声高に事を論ずる様のこともなく至極おとなしき人なり。 容貌を一見すれば豪気に見受けらるるも、万事温和に事を処する人なり。 但し胆力は極めて大なり。」 と、寺田屋事件の際にボディガード役として龍馬とともに奮戦した長州藩士・三吉慎蔵は、 龍馬の人柄について問われこう答えています。 私も「胆力」を身につけるべく日々修行です。(-_-;) ■ 至道無難(しどう・むなん) ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34938384.html 江戸前期の臨済宗の僧。「ぶなん」ともいう。 美濃(岐阜県)生まれ。 俗姓は相川。生家が関ケ原の本陣宿屋で,父が帰依した愚堂東寔が投宿した際に指導を受け, 「至道無難」の公案により徹悟し,法嗣となる。 出家した年には40歳前後,47歳と諸説ある。 江戸に出て麻布に東北庵を開き至道庵と号し, 延宝2(1674)年門人が建立した渋谷の東北寺の開山に招かれたが断り,小石川に移した。 2年後に示寂。徳川家綱の信頼を得たが名刹を避けた。 出家禅には批判的で,庶民的な庵主禅を説いた。 法嗣は白隠慧鶴の師道鏡慧端。 何事も 修行と思い する人は 身の苦しみは 消え果つるなり
- 雑 感 - 私の父の母校は、春、夏の高校野球長野県代表となる事が多く、 小さい頃より甲子園球場に連れて行ってもらいました。 その影響も有り、私は高校野球を見るのが大好きです。 彼らは失敗を恐れず、正々堂々と爽やかに全力を尽くして戦います。 試合後、勝敗に関わらず選手も監督も応援する母校の人達も「涙」を流します。 人目を気にせず、純粋な涙を流すその一瞬が見たいからなのかもしれません。 人が真剣に、一生懸命な時に流す涙はとても美しいです。 今日の言葉の意味は、 「人間は生きてゆく時、苦しい時の方が多い。 その困苦を修行と受け止めて人生に立ち向かうならば、 身の苦しみというのは消えてしまうものだ」 です。 私も高校球児に負けないよう、日々修行です。(-_-;) ■チャールズ・チャップリン ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34936572.html イギリスの映画俳優、映画監督、コメディアン、脚本家、映画プロデューサー、作曲家。 人に大切なのは、自信を持つことだ。
私が孤児院にいたとき、 腹をすかせて街をうろついて食いものをあさっていたときでも、 自分では世界一の大役者ぐらいのつもりでいた。 つまり勝ち気だったのだ。 こいつをなくしてしまったら、 人はうち負かされてしまう。 - 雑 感 - 私にも自信が有り勝ち気も持っています。 激動の時代に生きたチャップリンとは 比較対象にはならない程僅かなものですが。。。 自信とは 「自分で自分の能力や価値などを信じること。 自分の考え方や行動が正しいと信じて疑わないこと。」 と辞書に書いて有ります。 いったい自信とは何から生まれ、 どんな力を人に与えられるのだろう? 自信とは努力の結果から生ずるものだから、 不安を克服しながら、 絶えず目標に向かって 努力してきた人間が 得られるもの。 私もチャップリンのような大きな自信と勝ち気を身につけたいと思います。 日々修行です。(-_-;) ■ 吉田 松陰 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34935237.html 武士(長州藩士)、思想家、教育者、兵学者、地域研究家。 一般的に明治維新の精神的指導者・理論者として知られる。 一日一字を記さば一年にして三百六十字を得、
一夜一時を怠らば、百歳の間三万六千時を失う。 - 雑 感 - 私は幕末、明治維新の時代が今と似ていて好きで、 よく史跡めぐりをしています。 松下村塾の主宰者になり、高杉晋作、伊藤博文、山県有朋など、 後の維新指導者を輩出した、優れた思想家で兵学者でもある 吉田松陰の言葉です。 彼らはどんな思いで、この言葉を聞いていたのでしょうか? 私は無駄な時間を心の余裕と勝手に解釈してしまう 自分が恥ずかしくてなりません。 時間を疎かにしない考えを見習って・・ 日々修行です。(-_-;) ■ 内永 ゆか子 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34933513.html 経営者。英語スクールのベルリッツ・インターナショナルインク会長。 香川県出身。東京大学理学部物理学科卒業後、日本IBMに入社。 同社で専務まで勤め上げる。 その後退社し、NPO法人J−win理事長などを経て ベルリッツ・インターナショナルインク社長・会長。 そのほか、ベネッセコーポレーションの副会長なども務めた経営者。 主な著書に『部下を好きになってください』総理府男女共同参画審議会委員なども務めた。 米国女性エンジニア協会(SWE)アップワード・モビリティ賞受賞。 ぼやっとした思考やアイデアを誰かに話すと、相手から
「へぇ、そうなの?」 「それって何?」 「どうして?」 と反射的に素朴な疑問が返ってきます。 こうして対話しているうちに、 自分が何について理解できていないのかがわかってきます。 対話相手がサウンディング・ボード(音響反射板)の役割をしてくれるのです。 私がサウンディング・ボード役によく選んだのは専門知識を持たない母でした。 話していると自分の思考の中であやふやな部分が炙り出され、 課題の輪郭が見えてきます。 - 雑 感 - 私は、ぼやっとしたアイデアを社内でディスカッションして、 色々なアイデアを実現させてきましたが、最近特に思うのは、 他社でもやっているありふれた意見しか出てこない事に悩んでいました。 社内のスタッフは専門知識を持ち、 毎日仕事を追及する為に時間をついやしていたからで、 専門知識を持たない人とディスカッションする事で課題が見えてくるのかも! いつの間にか、専門バカになっていました。 皆様に喜んで頂け、ワクワク、ドキドキする仕事を始めなくては。 打つ手は無限ですよね。 日々修行です。(-_-;) ■ 道歌(どうか) ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34931588.html 道徳的な、または教訓的な短歌をいう。 様々な体験から出た世智であり、訓戒である。 昔から日本人に親しまれている。 堪忍(かんにん)の なる堪忍は 誰もする
な ら ぬ 堪 忍 す る が 堪 忍 - 雑 感 - 私の高校時代、毎週1回道徳の授業が有り、 教頭先生が教壇に立たれていました。 よく道歌を教えて頂き、今も心に残っています。 今日の言葉の意味は、 「もう我慢ならぬというところをじっと我慢することこそが、本当の我慢である。 最後まで耐え通さなければ、それまでの我慢もむだになる。」 です。 誰もするはずの堪忍さえできず、 ささいなことで堪忍袋の緒を切らす人が多い世の中ですが、 世界中の誰もがこの歌のような寛容の心境になれば 争い事は起きないと信じます。 私はまだ修養が足りません。 日々修行です。(-_-;) ■ 達磨大師 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34929962.html 達磨(だるま、ボーディダルマ)は禅宗の開祖とされている人物である。 菩提達磨(ぼだいだるま)、達磨祖師、達磨大師ともいう。 「ダルマ」というのは、サンスクリット語で「法」を表す言葉。 達摩との表記もあるがいわゆる中国禅の典籍には達磨、古い写本は達摩と表記する。) 気 は 長 く 、 心 は 丸 く 、 腹 を 立 て ず 、 人 は 大 き く 、 己 は 小 さ く 。
- 雑 感 - 私の学生時代は迷いの連続でした。 勉強しなくてはならない時期に、学業を放棄して北アルプスに登ってばかりで、 将来の夢も目標もなく、時間の尊さなんて微塵も感じる事がありませんでした。 そんな私を見かねて、ある日私は先生に呼ばれ、とても怒られました。 何を怒られたかは具体的に記憶に残っていないのですが、 書棚に置いてある土産物の達磨大師の木彫りを指差し、 眼光鋭く髭を生やした達磨大師のように迷わず腰を据えて生きる事を教えて頂きました。 私も木彫りの達磨大師を手に入れて今も書棚に置いているのですが、 毎日先生に怒られている気がします。 日々修行です。(-_-;) ■ 大隈 重信 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34928024.html 武士(佐賀藩士)、政治家、教育者。 位階勲等爵位は従一位大勲位侯爵。 政治家としては参議兼大蔵卿、外務大臣(第3・4・11・14・29代)、農商務大臣(第13代)、 内閣総理大臣(第8・17代)、内務大臣(第30・32代)、貴族院議員などを歴任した。 早稲田大学の創設者であり、初代総長である。 施 し て 報 を 願 わ ず 、 受 け て 恩 を 忘 れ ず 。
- 雑 感 - 私の祖父の座右の銘です。 言葉の意味は、 「人にしてあげたことは、その見返りを求めたり、まわりに吹聴したりせず、 人から受けた恩は決して忘れずにいること。」です。 「恩」という言葉の意味は、「他の人から与えられるめぐみ。 いつくしみ。また、自分のためになされたありがたい行為」と辞書に書かれています。 また、「恩」という漢字は、原因を心得ると書いて「為されたことを知る」という意味だそうです。 つまり、結果はもう出ていて、その結果において、因を知る。 また、原因の「因」の語源は、おふとんの上で人が大の字に寝ている様子を表します。 おふとんに人の型がついている。 そこには誰もいないけれど、おふとんに残ったその跡に、誰かがいたぬくもりが刻まれている。 もうそこにはないけれど、目の前にあるものを通して、その因として出遇えるものがある。 恩と因・・過去形でしか知りえないもの、それが本当のぬくもりというものなのかもしれません。 遠い昔に祖父から聞いた話しです。私はまだまだ未熟です。 日々修行です。(-_-;) ■ 山本 有三 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34926039.html 小説家、劇作家、政治家。 東京帝大在学中に芥川竜之介らと第3次「新思潮」を創刊劇作家、 小説家、政治家で日本芸術院会員、文化勲章受章者。 戦後、貴族院勅選議員、参議院議員などを歴任した。 たったひとりしかない自分を
たった一度しかない一生を ほんとうに生かさなかったら 人間うまれてきたかいが ないじゃないか 「路傍の石」より - 雑 感 - 私が社会人になる時に、祖父がこの言葉を贈ってくれました。 最近、この言葉をよく思い出します。 自分の人生を大切にするということは、 それそのものが周りの人、家族や友人をも大切にすること、 自分を祖末に扱うことは周りの人の人生を疎かにすることなんだと、 主人公の吾一少年に諭した言葉です。 私たちの人生は一度きりです。 私は今日という一日を「一度きり」の心意気を持ち、精一杯努力しているのか?。 結果、周りの人を疎かにしているのではないか? 日々修行です。(-_-;) ■ 老子 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34924184.html 古代中国の哲学者であり、道教創案の中心人物。 「老子」の呼び名は「偉大な人物」を意味する尊称と考えられている。 鐘や鼎のような大きな器は
簡単には出来上がらない。 人も、大人物は 才能の表れるのはおそいが、 徐々に大成するものである。 「老子」41章より - 雑 感 - 私は子供の時に、祖父より 「大器晩成」だと言われた事を今も鮮明に覚えています。 私の妹は勉強、運動、ピアノと秀でた部分が多々有ったのですが、 私は何をしてもダメ。(笑) 見かねた祖父のフォローだったと思うのですが、 感受性の高い子供の時に大器晩成と言われた為、 のんびりマイペースな生き方しかできないようにも感じています。 早咲き、遅咲き、ツボミのまま腐ってしまう花を見ていると、 一度は咲いてみたいと思います。 日々修行です。(-_-;) ■ 斉藤 里恵 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34922561.html ホステス、作家。青森県青森市出身。 自身の半生を描いた著書「筆談ホステス」が2009年(平成21年)にベストセラーとなった。 髄膜炎の後遺症で、1歳10カ月で聴力を完全に失う。 その後は「青森一の不良娘」と呼ばれるほどの問題児となるが、 万引した洋品店で誘われて働いたことをきっかけに、接客業の楽しさを知り、 19歳で水商売に進む。 2007年(平成19年)に単身上京し、東京・銀座の高級クラブでホステスとして働き、 筆談を駆使した独自の接客で大人気になり、ナンバーワンの地位に上り詰めた。 銀座で最初の店は八丁目の「Le Jardin」で、 当時の写真を同店のホームページで見ることができる 愛用するメモパットはRHODIAブロック(5mm方眼)。 星という字は、
日が生まれると書きます。 辛い時は『星』を見上げてください。 きっと明日が生まれます。 - 雑 感 - 私は小学5年生の時に星の魅力にとらわれ、 学校の図書館で星関係の本を夢中で読んでいました。 どうしても天体望遠鏡が欲しくなり、 小遣いで買える訳もなく、 両親に相談をしました。 で、天体望遠鏡を得る為の条件が、 生徒会の役員になる事。 私は人前で話す事が苦手で、 リーダーシップの微塵も有りませんでしたが、 天体望遠鏡欲しさに、 生徒会の役員に立候補してしまいました。 性格を見抜かれただけなのですが、 とてもいい経験をしたと両親に感謝しています。 今日の言葉には 「そして“明日”は、明るい日に違いありません」 と続きます。 私も明日を信じて今夜も星を眺めます。 日々修行です。(-_-;) ■ 坂東 眞理子 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34921035.html 官僚、評論家。 昭和女子大学学長を務める。 官僚として埼玉県副知事や豪州ブリスベン総領事、総理府男女共同参画室長、 内閣府男女共同参画局長などを歴任した人物であり、多くの女性政策に携わり、 2003年に退官。 以後は、昭和女子大学教授、副学長、女性文化研究所長を経て同大学の学長に就任。 また早くから執筆活動を行い、女性向けのライフスタイル書を数多く出版。 特に女性としての振舞い方をエッセイ風に説いた『女性の品格』は、 累計300万部を超えるベストセラーとなっている。 人生の理不尽さに遭遇したとき、
やがて日本人はこう口にします。 「しかたがない」と。 この言葉の中に私は、 日本人の強さと生きる知恵を みる思いがするのです。 「しかたがない」という言葉は、 英語のなかにはありません。 「しかたがない」と日本人が呟けば、 アメリカ人はこう言います。 「どうして諦めるんだ。逃げてはいけない。 どんな過酷なことがあったとしても、 ベストを尽くせば 必ず立ち直ることができる」と。 日本人は、けっして諦めの気持ちで この言葉を発しているのではありません。 この世の中には 人知を超えたものがある。 自分の力では どうしようもないことがある。 「なんで自分が」と思うことが 人生には必ず起こる。 そのことに抗っていても 道は見えてこない。 まずは受け止めること。 理不尽さや過酷な状況を 心でしっかりと受け止め、 そこから覚悟を決めて 歩き始めること。 その覚悟こそが、 日本人の底力なのだと 私は思っています。 - 雑 感 - 私は、祖父、父、母から「しかたがないねぇ」と言われ続け育ってきました。(笑) そして、私も口癖のように「しかたがない」とよく言葉にします。 今迄深く考えた事はありませんでしたが、自分ではどうしようもないことに対して、 それを「なんとかしなくちゃ」と思っても、焦るだけで何もできずに 時間とエネルギーを浪費してしまいます。 「しかたがない」と受け止めることで、そのことは置いておいて、 今できることをするほうが得策だし、希望が持てる事になる訳なんですね。 私にも底力があるのかな?期待外れと言われない為にも、日々修行です。(-_-;) ■ 野田 一夫 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34918985.html 経営学者。 事業構想大学院大学学長、 一般社団法人全国経営者団体連合会会長、 多摩大学名誉学長、 一般財団法人日本総合研究所会長、 高崎商科大学客員教授 などを務める。 うちの親父にはひとつの哲学があって、
それは明るい顔は周囲を明るくさせ、 暗い顔は周囲を暗くさせる。 だから、 人前に出たら暗い顔をしてはいけない、 というものです。 人間はみなそれぞれ人には言えない悩みをもっているものだが、 暗い顔は心の重荷をいっそう重くし、 笑顔は気持ちを軽くする。 だから、 みなさんもなるべく 笑顔を心がけるといいと思います。 - 雑 感 - 私は子供の頃、 面倒な事を言われると 直ぐに感情を顔に出す癖が有り、 怒られ続けてきました。 サラリーマン時代、 社内で思いっきり怒られて、 直後に笑顔で接客をさせられ、 それを何度も繰り返し行なう事で 感情をコントロールできるようになった 経験が有ります。 今思うに、 私を怒ってくれた上司、 先輩も大変だったんだなぁ、 と懐かしい思いでです。m(__)m ■ 手塚 治虫 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34917145.html 漫画家、アニメーター、アニメーション監督。 医学博士。血液型A型。 戦後日本においてストーリー漫画の第一人者として、 現代にまでにつながる日本の漫画表現の基礎を作った。兵庫県宝塚市名誉市民。 1963年、自作をもとに日本初となる30分枠のテレビアニメシリーズ『鉄腕アトム』を制作、 現代につながる日本のテレビアニメ制作に多大な影響を及ぼした。 1970年代には『ブラック・ジャック』『三つ目がとおる』『ブッダ』などのヒット作を発表。 また晩年にも『陽だまりの樹』『アドルフに告ぐ』など青年漫画においても傑作を生み出す。 デビューから1989年の死去まで第一線で作品を発表し続け、 存命中から「マンガの神様」と評された。 人を信じよ、
しかしその百倍も自らを信じよ。 時によっては、信じきっていた人々に 裏切られることもある。 そんなとき、 自分自身が強い盾であり、味方であることが、 絶望を克服できる唯一の道なのだ。 - 雑 感 - 手塚治虫さんの座右の銘と言われています。 私も人を信じるように努めています。 相手が嘘をついたとしても、 嘘を言わなくてはならない理由が有り、 それを暴く事が正しい事ではないと思うからです。 「甘い」、とか、「だから人に騙される」 と言われる事も多いのですが、 自分自身の生き方として、 私は人を信じます。 「人を真剣に愛したり信じたりしたりして裏切られたら・・」、 私は「いいじゃないか」と思います。 真剣に。自分を100倍も信じれるかというと・・。 まだまだ修行が足りません。(-_-;) ■ デニス・ウェイトリー ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34915442.html アメリカのモチベーション・スピーカー、自己啓発作家。 世界的に著名な脳力開発研究家の一人であり、ビジネスマンやスポーツ選手、 宇宙飛行士から学生まで、幅広いジャンルの人々を指導している能力・モチベーション開発の専門家。 米国航空宇宙局(NASA)でアポロ宇宙飛行士のストレスマネジメント、 米国オリンピック委員会で選手のメンタル面の強化、ベトナム戦争捕虜や イラン人質被害者のカウンセリングなども行った他、 南カリフォルニア大学客員教授、全米オリンピック委員会心理学部会委員長なども歴任している。 人生の様々なストレスを適正に評価し、
受け入れる最良の方法の一つは、 それを普通のことだと思うことだ。 - 雑 感 - 私はストレスをあまり感じないタイプになりました。 学生時代はストレスをため込む事が多かったのですが、 今迄の人生経験から、起きてしまった事実はどうする事もできないのですが、 その解釈は自分の考え方でどうにでもなる事に気付いたからです。 カウンセラー現場で使われる「りフレーミング」という技法と同じなのですが、 自分の考え方を少し工夫する事で、ストレスは軽減できるんだと思います。(^^) ■言葉の意味 リフレーミング(reframing)とは、 ある枠組み(フレーム)で捉えられている物事を枠組みをはずして、 違う枠組みで見ることを指す。 元々は家族療法の用語。 同じ物事でも、人によって見方や感じ方が異なり、 ある角度で見たら長所になり、また短所にもなる。 例えば、試験で残り時間が15分あった場合、 悲観的に考えた場合は「もう15分しかない」と思うし、 また楽観的に考えた場合は「まだ15分もある」と思うこと、など。 ■ 与謝野 鉄幹 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34913540.html 歌人。鉄幹は号。与謝野晶子の夫。後に慶應義塾大学教授。文化学院学監。 明治25年上京,落合直文に師事し浅香社に参加。 27年歌論「亡国の音」を発表し,和歌の革新をとなえる。 32年東京新詩社を創立して「明星」を創刊・主宰, 妻与謝野晶子(あきこ)とともに浪漫主義文学運動を推進した。 昭和10年3月26日死去。63歳。京都出身。本名は寛(ひろし)。 詩歌集に「東西南北」,歌集「相聞(あいぎこえ)」など。 妻をめとらば才たけて
みめ美(うる)わしく情(なさけ)ある 友をえらばば書を読みて 六分(りくぶ)の侠気(きょうき)四分の熱 恋の命をたずぬれば 名を惜しむかな男ゆえ 友の情けをたずぬれば 義のあるところ火をも踏む 汲めや美酒(うまさけ)うたひめに 乙女の知らぬ意気地あり 簿記(ぼき)の筆とる若者に まことの男君を見る あゝわれコレッジの奇才なく バイロンハイネの熱なきも 石を抱(いだ)きて野にうたう 芭蕉のさびをよろこばず - 雑 感 - 「人を恋うる歌」は16番まであり、私もたまに口ずさむ詩です。 どのような意味かというと、「男は理想と熱情を抱いて生きろ」です。 明治・大正・昭和初期の若者のロマン的で野心的で、かつ高踏的な気風がよく出ている詩です。 妻、友、我・・ 私は俗塵にまみれて自己嫌悪気味です。 久々に心を洗ってみたく歌ってみました。(-_-;) ■ 小村 寿太郎 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34911977.html 外交官、政治家。外務大臣、貴族院議員などを務めた。 侯爵。日向国飫肥藩(現在の宮崎県日南市のほぼ全域および宮崎市南部)の 下級藩士・小村寛平と梅子の長男として生まれる。 明治3年(1870年)、大学南校(東京大学の前身)に入学。 第1回文部省海外留学生に選ばれてハーバード大学へ留学し、法律を学んだ。 帰国後は司法省に入省し、大審院判事を経て、1884年に外務省へ転出する。 陸奥宗光に認められて、1893年に清国代理公使を務めた。 日清戦争(1894年-1895年)。 乙未事変の後、三浦梧楼に代わって駐韓弁理公使を務め、 在朝鮮ロシア総領事のカール・ヴェーバーと小村・ウェーバー覚書を交わした。 その後、外務次官、 1898年に駐米・駐露公使を歴任。 1900年(明治33年)の義和団の乱では、講和会議全権として事後処理にあたった。 1901年(明治34年)、第1次桂内閣の外務大臣に就任。 1902年(明治35年)、日英同盟を積極的に主張して締結に持ち込む。その功により男爵を授けられる。 日露戦争後の 1905年(明治38年)、ポーツマス会議日本全権としてロシア側の全権ウィッテと交渉し、 ポーツマス条約を調印。 もし私に誇るべきものがあるとしたら、
それはただ「誠」という言葉に 集約されるであろう。 つまるところ、 学問や同胞との付き合いでも、 また将来のことを考える場合でも、 この「誠」の心を忘れずに 貫く覚悟でいるのだ。 - 雑 感 - 私と私の祖父は時代劇が大好きで、私が中学生の時に、 京都の池田屋に連れて行ってもらい、後日、祖父より幕末に活躍した新撰組のシンボルマーク、 「誠」の文字を半紙に筆で書いてもらい宝物のように大切にしていました。 「誠」とは、本当のこと。 うそ・偽りのないこと。 誠実で偽りのない心。 すなおでまじめな心。 と辞書には書かれています。 今にして思えば、時代劇好きな私の性格を利用して 「誠」の心を教えてもらったのだと感じています。 私も常に「誠」の心を忘れずに 貫く覚悟でありたいと思います。(^^) ■ 正受老人(しょうじゅろうじん) 出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34910197.html 道鏡 慧端(どうきょう えたん、寛永19年10月22日〈1642年12月13日〉 享保6年10月6日〈1721年11月24日〉)は江戸時代の臨済宗の僧侶。 正受老人の名で知られている。 信州松代藩主真田信之の庶子。 19歳で出家し、至道無難などの指導を受ける。 臨済宗中興の祖と称される白隠慧鶴の師で、 白隠が大悟したと思い込み慢心していたところを厳しく指導し、 正しい悟りに導いた。 吾れ世の人と云ふに、
一日暮らしといふを工夫せしより、 精神すこやかにして、又養生の要を得たり。 如何ほどの苦しみにても、一日と思へば堪へ易し。 楽しみも亦、 一日と思へば耽(ふけ)ることあるまじ。 一日一日と思へば、退屈はあるまじ。 一日一日をつとむれば、百年千年もつとめやすし。 一大事と申すは、今日只今の心也。 - 雑 感 - 正受老人は、 「今日すべき事を翌日に持ち越さず、今日する事は今日きちんとやり、 そして今日は自分ながら一生懸命やったな。 と言う満足感を得られるような暮らしを心掛けたいものだ。 今日の事は今日始末せよ。」 とおっしゃっています。 私は明日があると思うから、 その日のことを怠りがちになり、 困難な事は後回しにして、 明日やればいいと、 ほどほどに過ごしてしまいがちです。 私は「1年の計は元旦にあり」と考えていても、 今ここににいる、この一刻の、この今を どう生きるか暮らすかを考えていませんでした。 親孝行もそのうちに・・、と。日々修行です。(-_-;) ■ スティーブ・ジョブズ ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34908220.html アメリカ合衆国の実業家。 スティーブ・ウォズニアックらと共に、商用パーソナルコンピュータで 世界初の成功を収めたアップル社の共同設立者の一人。 また、そのカリスマ性の高さから、発言や行動が常に注目を集め続けた。 すばらしい仕事をするには、
自分のやっていることを 好きにならなくてはいけない。 まだそれを見つけていないのなら、 探すのをやめてはいけない。 安住してはいけない。 心の問題のすべてがそうであるように、 答えを見つけたときには、 自然とわかるはずだ。 - 雑 感 - 私は、花屋を生業とする前に工業系の会社で働いていました。 阪神大震災に被災した経験から、花の仕事というよりも、 「人の真心・気持ち」を扱える仕事がしたいと思うようになり、 会社を辞めて花屋になりました。 天職と思い、毎日を精一杯生きています。(*^^)v ■ 坂村 真民 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34906547.html 仏教詩人。一遍の生き方に共感し、癒しの詩人と言われる。 愛媛県砥部町に「たんぽぽ堂」と称する居を構え、毎朝1時に起床し、 近くの重信川で未明の中祈りをささげるのが日課であった 。詩は解りやすい物が多く、小学生から財界人にまで愛された。 特に「念ずれば花ひらく」は多くの人に共感を呼び、その詩碑は 全国、さらに外国にまで建てられている。 森信三が早くからその才覚を見抜き後世まで残る逸材と評した。 昼の月を見ると
母を思う こちらが忘れていても ちゃんと見守って下さる 母を思う かすかであるがゆえに かえって心にしみる 昼の月よ - 雑 感 - 私は、人生で苦しい事、辛い事が有ると坂村真民さんの詩を読み返しています。 坂村真民さんのお母さんは、36才で未亡人になり、女手一つで5人の子供達を育て、 母をテーマにした詩も多く書かれています。 昼間に、ふと空を見上げて、白く透けるような月を見るたびにこの詩と、 そして母のことが思い浮かびます。 親孝行・・とても簡単なようで難しいです。 詩を読んで自分の人生を振り返ると恥ずかしくなってしまいます。 頑張らなくてはと思うのですが、なかなか気持ちが継続できません。 日々修行です。(-_-;) ■ 吉野 弘 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34904177.html
詩人。山形県生まれ。 1942年、旧制の商業学校を戦時繰り上げ卒業。 徴兵検査に合格したが、入隊直前に終戦を迎えた。 石油会社に入り労働組合活動に携わるが、結核のため療養中に詩作を始めた。 53年、川崎洋らの詩誌「櫂(かい)」に参加した。 「I was born」を含む第1詩集「消息」(57年)で、 生活者の痛みを澄明な言葉で表現する戦後詩人として注目を浴びた。 「感傷旅行」(71年)で読売文学賞、「自然渋滞」(89年)で詩歌文学館賞を受賞。 他の詩集に「幻・方法」「北入曽」「陽を浴びて」など。 評論「現代詩入門」も広く読まれた。 2014年1月15日21時48分、肺炎のため静岡県富士市の自宅で死去した(87歳) いつものことだが
電車は満員だった。 そして いつものことだが 若者と娘が腰をおろし としよりが立っていた。 うつむいていた娘が立って としよりに席をゆずった。 そそくさととしよりが坐った。 礼も言わずにとしよりは次の駅で降りた。 娘は坐った。 別のとしよりが娘の前に 横あいから押されてきた。 娘はうつむいた。 しかし 又立って 席を そのとしよりにゆずった。 としよりは次の駅で礼を言って降りた。 娘は坐った。 二度あることは と言う通り 別のとしよりが娘の前に 押し出された。 可哀想に 娘はうつむいて そして今度は席を立たなかった。 次の駅も 次の駅も 下唇をキュッと噛んで 身体をこわばらせて−−。 僕は電車を降りた。 固くなってうつむいて 娘はどこまで行ったろう。 やさしい心の持主は いつでもどこでも われにもあらず受難者となる。 何故って やさしい心の持主は 他人のつらさを自分のつらさのように 感じるから。 やさしい心に責められながら 娘はどこまでゆけるだろう。 下唇を噛んで つらい気持ちで 美しい夕焼けも見ないで。 - 雑 感 - 私は吉野弘さんの詩の中で、少し切なくて胸キュンとなってしまうこの詩が大好きです。 満員電車で「お年寄り」に席を譲る事って、当たり前の事なのですが、 今の世の中できない人がいっぱい居ます。 席を譲られる事に感謝される人も居れば、 まだ年寄り扱いされたく無いと席を譲られる事に抵抗感を持つ人も居ます。 3番目の「としより」と思われる人には、あえて席を譲らず、 その人の心を傷つけないようにじっと唇を噛んで時が経つのを待っている、 娘さんの優しさを感じてしまいます。 優しい人は、優しいゆえに、人の心の痛みがわかり、傷つくことも多いから・・。 女の子が気づかなかった美しい夕焼けとは、女の子の心の美しさかなぁ、と思います。(^^) 吉野弘さんのご冥福をお祈りします。
|
|||||
この記事に