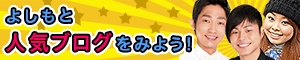■ 斎藤 一人 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35083832.html 実業家。「銀座まるかん」の創業者。 1970年頃から漢方茶の販売を開始。 その後、漢方をベースにした化粧品や健康食品の開発に着手し、 銀座日本漢方研究所(現・銀座まるかん)を創業する。 観音信仰と経営体験に基づいた独自の人生観を持ち、 それらを論じた人生訓・自己啓発に関する関連書籍などを出版している。 「私はプロですから、
こんなことは当たり前です。」 と言えるようになると、 たいがいの事は怖くありません。 ■ 桃井 和馬 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35081222.html 写真家、ジャーナリスト。東京都出身。 テンプル大学日本校アメリカ研究学科卒業。 世界140カ国を取材し、紛争・地球環境などを題材に宗教的な文明論を展開している。 第32回太陽賞受賞。 一瞬一瞬を乗り切る。
それを積み重ねると、 いつの間にか、 最も苦しい時間を 乗り切ることができる。 見えない未来に 心が折れそうな時は、 一日だけを乗り切ることに 集中する。 ■ 大塩 平八郎 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35079277.html 江戸時代後期の儒学者、大坂町奉行組与力。 大塩平八郎の乱を起こした。 山中の賊に克(か)つことは易しく
心中の賊に克つことは難し ■ 鍵山 秀三郎 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35077496.html 株式会社ローヤル(現 イエローハット)の創業者。 また、日本を美しくする会の相談役でもある。 掃除をテーマにした活動・講演を全国各地で行なっている。 成功のコツは2つ。
それは「コツコツ」。 ■ 喜多川 泰 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35075370.html 作家。愛媛県立西条高等学校、東京学芸大学卒業。 卒業後教育者を目指し大手の学習塾に就職、後に独立し1998年横浜に新たな学習塾を立ち上げた。 塾生の学習意欲を高めたり人生教訓を教える為、毎度授業の前の時間を使って話をしていたが、 ある塾生からそれらの話を本にまとめてみたらどうかといわれたのを切っ掛けとし、 本業の傍ら、自身のデビュー作となる2005年にファンタジー風の自己啓発書『賢者の書』を執筆、 ディスカヴァー・トゥエンティワンから出版した。 「親孝行」とは、
経済的援助をしたり、 旅行や物をプレゼントすること だと思っていました。 でも、親となり、 親として一番幸せな瞬間は、 子どもが人の役に立ち、 人から喜ばれる存在になった時だと、 初めて知りました。 ■ 久保田 美文 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35073276.html 実業家。 元ダイセル化学工業社長。 「己の長を以って人の短をあらわすなかれ」
人は往々にして自分の長所を標準として 他人の短所を責めがちなんです。 ■ 澤田 秀雄 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35071632.html 実業家。 エイチ・エス証券株式会社代表取締役社長。 株式会社エイチ・アイ・エス取締役会長。 2003年3月よりモンゴルAG銀行(現・ハーン銀行)の取締役会長。 2010年4月よりハウステンボス社長。 大阪市立生野工業高等学校を卒業後、1973-1976年まで、旧西ドイツ・マインツ大学に留学。 留学中、アルバイトで稼いだ資金を元手に、ヨーロッパ、中東、アフリカ、南米、アジアなど 50か国以上を旅行する。 帰国後、1980年に上京し新宿西口に旅行会社「株式会社インターナショナルツアーズ」を登録・設立。 格安航空券販売を中心に、航空券とホテルを組み合わせた個人旅行、パッケージ旅行の販売を手がける。 常にチャレンジし続けることです。
新しいことにチャレンジして 会社を変化させないと、 時代に取り残されてしまいます。 ■ 坂村 真民 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35069604.html 仏教詩人。一遍の生き方に共感し、癒しの詩人と言われる。 愛媛県砥部町に「たんぽぽ堂」と称する居を構え、毎朝1時に起床し、 近くの重信川で未明の中祈りをささげるのが日課であった。 詩は解りやすい物が多く、小学生から財界人にまで愛された。 特に「念ずれば花ひらく」は多くの人に共感を呼び、 その詩碑は全国、さらに外国にまで建てられている。 森信三が早くからその才覚を見抜き後世まで残る逸材と評した。 深海の真珠のように
ひとりひそかに 自分をつくってゆこう ■ 三木 建 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35068192.html 企業の「思想論」「文化論」「変革論」を専門に米国経営大学院で教鞭を取ってきた経営学者。 事業経営と組織経営の2つの領域から企業経営を成長に導くという組織経営論を提唱し、 理論を実践に移す専門機関としてGray Institute of Managementを設立。 多くの企業の経営会議顧問として経営の指導にあたっている。) 国家でも企業でも
勝つの負けるのと言ってる間は未熟である。 強い国を目指すなら、 魅力的な文化を発信し、 一貫した公平で崇高な意思を 堂々と主張することから 身に付けなくてはならないだろう。 強い企業を目指すなら、 まず無二の存在へ向けて 舵を切らなくてはならない。 真の強さとは 戦わずして勝つことである。 その「強さ」の上の次元に 人々の求める「良さ」がある。 ■ 橋本 武 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35066375.html 国語教師、国文学者、元灘校(灘中学校・高等学校)教頭。京都府宮津市出身。 中学の3年間をかけて中勘助の『銀の匙』を1冊読み上げる国語授業「『銀の匙』授業」で知られる。 実際の授業では単に作品を精読・熟読するだけではなく、 頻繁に横道に逸れ、国語の授業の枠に留まらない授業スタイルをとっていた。 灘校を退職後は地元の予備校や文化教室で講師として精力的に活動を続け、 2011年に灘校の特別授業「土曜講座」で再び教壇に立ち、27年ぶりとなる「銀の匙授業」を行った。 主な著書・関連書籍に 「伝説の灘校教師が教える一生役立つ学ぶ力」 「日本人に遺したい国語 101歳最後の授業」 などがある。 「これを言ってもいいか。
これをしてもいいか。 それによって相手はどう感じるだろうか。 そういうことを 一瞬でもいいから考えなさい」。 これは私が生徒たちに 必ず言ってきた言葉です。 この気持を忘れてしまうと、 人間はとても傲慢な生き物に なり下がってしまう。 ■ 佐々木 正 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35064472.html 電子工学の技術者。シャープ元副社長。工学博士。「ロケット・ササキ」の異名を持つ。 大卒後、当時の川西機械製作所(現富士通)へ入社。 昭和30年代に早川電機工業(現:シャープ)の要請を受け転進。 シャープ株式会社専務、副社長を経て現在同社顧問。 ポケットに入る超小型電卓の開発により液晶業界では世界的に最も著名な研究者。 ソフトバンク(株)相談役、(株)国際基盤材研究所代表取締役、郵政省電波技術審議会委員、 新エネルギー財団・太陽光エネルギー委員会委員長、(財)国際メディア研究財団理事長、 (財)未踏科学技術協会理事、島根/テキサス産業技術共創委員会島根側共創委員会委員長ほか 数多くの要職に就く。 現在は氏の私塾の「正道塾」を通じ、後進の育成にあたっている。 孔子は73歳で死んでいますから、
『論語』には「七十にして矩(のり)をこえず」の次はありません。 97歳の私が言うならば、「八十にして恩を知る」でしょうか。 人間は自分一人でなく、いろんな人のおかげで生きとるんです。 そして、「九十にして今度は恩に報いる」。 そうすれば百で人生を終えるとき、幸福でいられるはずです。 ■ 森 信三 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35062725.html 哲学者・教育者。 徳永康起遺文集にも記載されている通り、上記の文章を精力的に広めることを推奨していた。 天王寺師範学校(後の大阪教育大学)の専攻科講師を経て、1939年に旧満州の建国大学に赴任。 敗戦後の1946年に帰国し、翌年に個人雑誌「開顕」を創刊。 その後、神戸大学教育学部教授や神戸海星女子学院大学教授などを歴任。 1975年に「実践人の家」を建設。 全国各地で講演を行ない、日本民族再生に大きく働きかけた。 とにかく人間は徹底しなければ駄目です。
もし徹底することができなければ、 普通の人間です。 ■ 松田 伊三雄 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35059817.html 実業家。元三越社長。1919年(大正8年)慶應義塾大学卒業後、三越本店に入社。 入社後の苦労は相当なものだった。 和服に前掛け姿。初めは通信販売の仕事に携わったが、 残業に次ぐ残業で連日帰宅は夜11時をまわっていた。 「古い番頭からは、“学校出だ”としごかれ、慶大から入社した13人が、 半年も経たぬ内に3人になってしまった」。 そして1924年(大正13年)の関東大震災。 降って沸いたようなこの大惨事で東京の本店は完全にまひした。 「三越はもうダメだ」と、大阪の百貨店への就職を頼み込んだが、逆にたしなめられる。 一念発起してがむしゃらに働き、1930年(昭和5年)5月、主任から京城支店次長へスピード出世する。 そして足かけ9年間で、京城支店を売上高第2位の大阪支店に匹敵する優秀店に育て上げた。 そのキャリアが買われ、1938年(昭和13年)大阪支店次長に就任。 同支店次長時に、部下が客を万引と思い違いをし店長名の謝罪文を要求された。 客は理髪店主で、身の潔白を証明するため、店の入り口にその謝罪文を貼っておくという。 松田は部下の責任を一身に背負い、20日間1日も休まず理髪店に通い、散髪やひげそりをしてもらった。その誠意に店主は心動かされ『謝罪文の代わりに、三越のポスターを持って来なさい。 店に貼ってあげよう』といってくれた。松田は誠意を尽くすことで危機を見事に乗り切った。 誠意をもって接すれば、
人の心は通じ合い、 人の心をつかむこともできる。 ■ 坂村 真民 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35057791.html 仏教詩人。一遍の生き方に共感し、癒しの詩人と言われる。 愛媛県砥部町に「たんぽぽ堂」と称する居を構え、毎朝1時に起床し、 近くの重信川で未明の中祈りをささげるのが日課であった。 詩は解りやすい物が多く、小学生から財界人にまで愛された。 特に「念ずれば花ひらく」は多くの人に共感を呼び、 その詩碑は全国、さらに外国にまで建てられている。 森信三が早くからその才覚を見抜き後世まで残る逸材と評した。 順調に行く者が
必ずしも幸せではないのだ 悲しむな タンポポを見よ 踏まれても平気で 花を咲かせているではないか - 雑 感 - 私の住む地域では、今日がお花見真っ盛りです。 桜も今日、明日が見納め、今年も桜を見ながら一杯という時間が有りませんでした。 春に咲くタンポポ、大好きなんです。 可愛い黄色の花を咲かせ、綿帽子なんかもたまりません。 子供の頃には感じませんでしたが、生命力の強さに惹かれてます。 どんな境遇に生まれ育つかは選択できなくても、 とにかく自分なりの花を咲かせることの大切さを タンポポの姿が教えてくれているようです。 日々修行です。(-_-;) ■ 八木 重吉 ◇出典 : http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35051276.html 「神を呼ぼう」より 詩人。東京府南多摩郡堺村(現在の東京都町田市相原町)に生まれる。 神奈川県師範学校(現・横浜国立大学)を経て、東京高等師範学校の英語科を1921年に卒業。 兵庫県の御影師範学校(現・神戸大学)、 次いで1925年から千葉県の柏東葛中学校(現・千葉県立東葛飾高等学校)で英語教員を務めた。 神奈川県師範学校在学時より教会に通いだすようになり、 1919年には駒込基督会において富永徳磨牧師から洗礼を受けた。 人が私を褒めてくれる
それが何だろう 泉のように湧いてくるたのしみのほうがよい 神ひとつに生き そしてどこに怒りがあるか 許しうるものを許す それだけならどこに神の力が要るか 人間に許しがたきを許す そこから先は神のためだと知らぬか ゆるされ難い私がゆるされている 私はたれをも無条件でゆるさねばならぬ ■ 星野 富弘 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35041299.html 詩人・画家。 1970年(昭和45年)に群馬大学を卒業し。 中学校の体育教師になるが、クラブ活動の指導中、頸髄を損傷、手足の自由を失う。 1991年(平成3年)、群馬県勢多郡東村(当時)の草木湖のほとりに、 星野富弘の作品を展示する村立富弘美術館が開館した。 「人生が二度あれば」 とは、
今の人生を諦めてしまうから 出てくる言葉です。 今を精一杯生きられないで、 どうして次の人生を しっかり生きられるでしょう。 ■ マザー・テレサ ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35039504.html カトリック教会の修道女にして修道会「神の愛の宣教者会」の創立者である。 「マザー」は指導的な修道女への敬称であり、「テレサ」は修道名である。 カトリック教会の福者。 コルカタ(カルカッタ)で始まったテレサの貧しい人々のための活動は、 後進の修道女たちによって全世界に広められている。 生前からその活動は高く評価され、 1973年のテンプルトン賞、 1979年のノーベル平和賞、 1980年のバーラ・ラトナ賞(インドで国民に与えられる最高の賞)、 1983年にエリザベス2世から優秀修道会賞など多くの賞を受けた。 1996年にはアメリカ名誉市民に選ばれている(アメリカ名誉市民はわずか7人しかいない)。 2003年10月19日、当時の教皇ヨハネ・パウロ2世によって列福された。 導いてくれる人を
待っていてはいけません。 あなたが人々を導いていくのです。 ■ 相田 みつを ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35037339.html 詩人・書家。平易な詩を独特の書体で書いた作品で知られる。 書の詩人、いのちの詩人とも称される。 相田は書の最高峰のひとつとされる毎日書道展に1954年から7年連続入選するなど、 技巧派の書家として出発した。 1947年の鄭道昭の臨書・「鄭文公碑臨書」で古典書道における実力を示す一方、 1950年に栃木県芸術祭書道中央展に出品した「宿命」では、 伝統的な書道界に対する複雑な思いを詩文書の形で吐露。 専門家でなければ理解しにくい書のあり方に疑問を抱き、 「書」と「詩」の高次元での融合を目指すようになり、 三十歳のころ、独特の書体で、短く平易な自らの言葉を書く作風を確立した。 人生において
最も大切な時 それはいつでも いまです ■ 千宗室(15代) ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35035782.html 茶道裏千家前家元15代汎叟宗室。 父は通称「淡々斎宗室」として知られる14代碩叟宗室。 学徒動員により海軍に入隊し、予備学生飛行科に採用され士官としての訓練を受け、 自身の意思で特別攻撃隊(特攻隊)に志願。 多くの仲間が特攻隊として出撃し、自身も突撃命令を受けようとしたときに終戦を迎え除隊。 終戦後に同志社大学法経学部経済学科に復学した後、 大徳寺の管長後藤瑞巌老大師のもとで修行生活を送る。 1964年に千利休居士15代裏千家今日庵家元宗室を襲名。 藍綬褒章、紫綬褒章、文化功労者、勲二等旭日重光章、文化勲章などを受賞。 作務で草むしりをしていた私に
老師はこう問いかけたのです。 「あんた、どんな気持ちで 草を抜いてるんや」 と。 「あんたが何気なく抜いてる草も、 生きてるんやで。 他の草を生かすために、 その草の命を奪っているわけや。 生かされているということが、 どんなに尊いことなのか、 そのことに心を馳(は)せなさい」。 ■ 親鸞聖人◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35033654.html
鎌倉時代前半から中期にかけての日本の僧。 浄土真宗の宗祖とされる。 明日ありと
思ふ心のあだ桜 夜半に嵐の吹かぬものかは - 雑 感 - 私は桜の季節になると、祖父と一緒に京都の桜を見に行っていました。 桜を見るたびにいろんなことを考えさせられます。 凛とした強さ、桜に逢いたくてたまらなくなります。 今日の言葉は、この時期よく京都のお寺の掲示板に貼ってあり、 毎年思い出してしまいます。 親鸞聖人が9歳の時、出家しようと慈円和尚の元へ行ったとき、 既に夜も更けていたので慈円和尚が 「今夜はとりあえず休め」と言ったところ、 この歌を詠ったとされています。 言葉の意味は、今は盛大に咲き誇っていても、 夜半に嵐が吹けば桜は一瞬にして散ってしまう。 世は無常であって、やるべきことは必ずできる時にやって、 明日桜を見に行こうというが如き気持ちではいけないということ。 人間のことを桜に例えて戒めた歌です。 私にはとても身に沁みます。 日々修行です。(-_-;)
|
|||||
この記事に