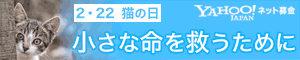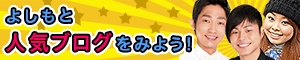■ 勝本 華蓮 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35127920.html 1955年大阪府生まれ。 1991年、天台宗青蓮院門跡にて得度(現在も所属)。 京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。 博士(文学)。専攻はインド仏教学・パーリ学。 花園大学非常勤講師、叡山学院専任講師、ケラニヤ大学パーリ学仏教学大学院客員研究員等を経て、 現在、東方学院講師・叡山学院講師。 著書に 『座標軸としての仏教学』、 『現代と仏教』(ともに佼成出版社)、 『チャリヤーピタカ註釈』(国際佛教徒協会)等のほか、 翻訳書『原始仏典』第6巻・第7巻(共訳、春秋社)があり、 研究論文を多数執筆。 最近は雑誌『サンガジャパン』第4号での対談やNHK教育テレビ「こころの時代」に 出演など活動を広げる。 幸不幸は、過去と現在、他人と自分を
比較して妄想しているだけで、 主観的・相対的なものだ。 この世のものはすべて変化するから、 何かに執着すると苦が生まれる。 「この世は苦」が仏教の基本。 「そうだ。もともと苦なんだ」 と基準を下げると、 プラス面が見えて、 心がうんと軽くなりますよ。 - 雑 感 - えっ、「この世は苦」が基本なんですか。 だとしたら、全然大丈夫じゃないですか。(笑) 私は比較の考えをして不幸になっていることが多いのかもしれません。 なかなか幸せになれないのは、幸せの基準が高いからかかもしれません。 日々修行です。(-_-;) ■ マザー・テレサ ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35125843.html カトリック教会の修道女にして修道会「神の愛の宣教者会」の創立者である。 「マザー」は指導的な修道女への敬称であり、「テレサ」は修道名である。 カトリック教会の福者。コルカタ(カルカッタ)で始まったテレサの貧しい人々のための活動は、 後進の修道女たちによって全世界に広められている。 生前からその活動は高く評価され、 1973年のテンプルトン賞、 1979年のノーベル平和賞、 1980年のバーラ・ラトナ賞(インドで国民に与えられる最高の賞)、1983年にエリザベス2世から優秀修道会賞など多くの賞を受けた。 1996年にはアメリカ名誉市民に選ばれている(アメリカ名誉市民はわずか7人しかいない)。 2003年10月19日、当時の教皇ヨハネ・パウロ2世によって列福された。 いつもお互いに笑顔で会うことにしましょう。
笑顔は愛の始まりですから。 Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. ■ マクシム・ゴーリキー ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35124025.html ロシアの作家。 本名はアレクセイ・マクシーモヴィチ・ペシコフ (Алексей Максимович Пешков)。 ペンネームのゴーリキーとはロシア語で「苦い」の意味。 社会主義リアリズムの手法の創始者であり、社会活動家でもあった。 信じるのだ。
こんなちっぽけな人間でも、 やろうとする意志さえあれば、 どんなことでもやれるということを。 ■ 吉川 英治 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35120880.html 小説家。、『鳴門秘帖』などで人気作家となる。 1935年(昭和10年)より連載が始まった『宮本武蔵』は広範囲な読者を獲得し、 大衆小説の代表的な作品となった。 戦後は『新・平家物語』、『私本太平記』などの大作を執筆。 幅広い読者層を獲得し、「国民文学作家」といわれる。 行き詰まりは、
展開の一歩である。 ■ 石田 退三 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35119081.html 元豊田自動織機製作所(現豊田自動織機)社長、 元トヨタ自動車工業(現トヨタ自動車)の社長・会長・相談役。 戦後のトヨタ自動車の建て直しをし、豊田英二と共に「トヨタ中興の祖」と呼ばれる。 石田は無駄をとことん嫌い、無駄なお金を一切使わなかったといわれる。 これはトヨタの危機の際に累積赤字が蓄積し銀行に融資を断られたという苦い思い出があり、 「自分の城は自分で守れ」と、内部留保をとことん増やして 自前で必要な機械などを買うというやり方を行っていた。 この方針は現在でも受け継がれ、トヨタは「トヨタ銀行」と呼ばれるほど内部留保を多く持っている。 なおこの経営危機の際、当時の融資銀行だった東海銀行、三井銀行が支援した反面、 住友銀行は真っ先に融資回収に走ったため、終生、住銀との取引を許さなかった 人生はすべて勝負だ。
勝負は闘志と 努力がすべてである。 ■ アルベルト・アインシュタイン ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35117073.html ドイツ生まれのユダヤ人理論物理学者。 特殊相対性理論及び一般相対性理論、相対性宇宙論、 ブラウン運動の起源を説明する揺動散逸定理、光量子仮説による光の粒子と波動の二重性、 アインシュタインの固体比熱理論、零点エネルギー、半古典型のシュレディンガー方程式、 ボーズ=アインシュタイン凝縮などを提唱した業績により、 20世紀最大の物理学者とも、 現代物理学の父とも呼ばれる。 「人間は何のために生きているのですか?」
と日本の学生に質問されて 他人を喜ばすためです。 そんなことがわからないんですか? ■ 武者小路 実篤 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35115149.html 小説家・詩人・劇作家・画家。 藤原北家の支流・閑院流の末裔で江戸時代以来の公卿の家系である武者小路家に 武者小路実世子爵の第8子として生まれた。 2歳の時に父が死去。子供時代は作文が苦手だった。 学習院初等科、同中等学科、同高等学科を経て、 1906年(明治39年)に東京帝国大学哲学科社会学専修に入学。 1907年(明治40年)、学習院の時代から同級生だった志賀直哉や木下利玄らと「一四日会」を組織する。 同年、東大を中退。 1908年(明治41年)、回覧雑誌『望野』を創刊。 1910年(明治43年)には志賀直哉、有島武郎、有島生馬らと文学雑誌『白樺』を創刊。 彼らはこれに因んで白樺派と呼ばれた。 実篤はトルストイに傾倒したが、その彼はまた白樺派の思想的な支柱だった。 一から一をひけば零である。
人生から愛をひけば何が残る。 土地から水分をとれば 沙漠になるようなものだ。 ■ マザー・テレサ ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35113244.html カトリック教会の修道女にして修道会「神の愛の宣教者会」の創立者である。 「マザー」は指導的な修道女への敬称であり、「テレサ」は修道名である。カトリック教会の福者。 コルカタ(カルカッタ)で始まったテレサの貧しい人々のための活動は、 後進の修道女たちによって全世界に広められている。 生前からその活動は高く評価され、 1973年のテンプルトン賞、 1979年のノーベル平和賞、 1980年のバーラ・ラトナ賞(インドで国民に与えられる最高の賞)、 1983年にエリザベス2世から優秀修道会賞など多くの賞を受けた。 1996年にはアメリカ名誉市民に選ばれている(アメリカ名誉市民はわずか7人しかいない)。 2003年10月19日、当時の教皇ヨハネ・パウロ2世によって列福された。 微笑みが平和への第一歩なのです。
A smile is the beginning of peace. ■ 桐木 千寿 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35109636.html 大阪府出身の元芸妓、華道家、祇園コンシェルジュ。 祇園甲部の芸妓として高い人気を誇った人物であり、 お座敷や都をどりだけでなく多数のメディアにも出演。 白洲次郎などの著名人との交流でも知られている。 36歳で舞妓を引退した後は、華道家に転身したほか、 花街の案内役・祇園コンシェルジュとしても活躍している。 人とのかかわりで
苦手意識を持たないこと。 嫌いなタイプは誰にもあります。 会った瞬間、この人苦手と思うのは 誰しもあること。 でも相手も 嫌いと思ってますよ。 相手を好きになると 相手にも好かれるのです。 心をほぐしてあげると ひらいてもらえます。 これこそ、日本が海外に誇れる “おもてなし術”です。 ■ 阿部 由晴 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35107885.html 秋田県生まれ・宮城県育ちのサッカー指導者、教育者。 常盤木学園高等学校サッカー部の名監督として知られる人物であり、 女子サッカー日本代表選手・プロ女子サッカー選手を多く輩出している。 「他利の精神」
に基づく目的を 探してみてください。 他利の精神とは、 そのことを通して、社会が良くなる、 多くの人に喜ばれるということです。 そんな「目的」を一人ひとりが 抱いているだけで社会が変わります。 ■ ジョン・ラスキン ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35106437.html 19世紀イギリス・ヴィクトリア時代を代表するの評論家・美術評論家である。 同時に芸術家のパトロンであり、設計製図や水彩画をこなし、 社会思想家であり、篤志家であった。 何を考えているか、
何を知っているか、 何を信じているかは、 それほど重要なことではない。 唯一重要だと言えるのは、 何をするかだ。 ■ 坂村 真民 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35104624.html 仏教詩人。 一遍の生き方に共感し、癒しの詩人と言われる。 愛媛県砥部町に「たんぽぽ堂」と称する居を構え、毎朝1時に起床し、 近くの重信川で未明の中祈りをささげるのが日課であった。 詩は解りやすい物が多く、小学生から財界人にまで愛された。 特に「念ずれば花ひらく」は多くの人に共感を呼び、その詩碑は全国、 さらに外国にまで建てられている。 森信三が早くからその才覚を見抜き後世まで残る逸材と評した。 サラリと
生きてゆかん 雲のごとく サラリと 忘れてゆかん 風のごとく サラリと 流してゆかん 川のごとく ■ 伊藤 博文 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35099981.html 武士(長州藩士)、政治家。 位階勲等爵位は従一位大勲位公爵。 周防国出身。長州藩の私塾である松下村塾に学び、幕末期の尊王攘夷・倒幕運動に参加。 維新後は薩長の藩閥政権内で力を伸ばし、岩倉使節団の副使、参議兼工部卿、 初代兵庫県知事(官選)を務め、大日本帝国憲法の起草の中心となる。 初代・第5代・第7代・第10代の内閣総理大臣および初代枢密院議長、初代貴族院議長、 初代韓国統監を歴任した。 内政では、立憲政友会を結成し初代総裁となったこと、 外交では日清戦争に対処したことが特記できる。元老。 いやしくも天下に
一事一物を成し遂げようとすれば、 命懸けのことは始終ある。 依頼心を起こしてはならぬ。 自力でやれ。 ■ ヘンリー・フォード ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35096309.html アメリカ合衆国出身の企業家、 自動車会社フォード・モーターの創設者であり、 工業製品の製造におけるライン生産方式による大量生産技術開発の後援者である。 フォードは自動車を発明したわけではないが、アメリカの多くの中流の人々が購入できる 初の自動車を開発・生産した。 カール・ベンツが自動車の産みの親であるなら、自動車の育ての親はヘンリー・フォードとなる。 T型フォードは、世界で累計1,500万台以上も生産され、産業と交通に革命をもたらした。 フォード・モーターの社主として、世界有数の富豪となり、有名人となった。 安価な製品を大量生産しつつ労働者の高賃金を維持する「フォーディズム」の創造者である。 フォードはまた、消費者優先主義が平和の鍵だというグローバルなビジョンを持っていた。 体系的なコスト削減を強力に推進し、多くの技術革新やビジネス上の革新をもたらした。 ほとんどの人が、
成功とは手に入れるもの だと考えています。 でも本当のところ、 成功とは与えることなのです。 ■ 兼子 ただし ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35094340.html スポーツストレッチングトレーナー兼株式会社スリーエスグループジャパンの代表取締役である。 茨城県出身。大妻女子大学のOMA講師を務める。 新日本キックボクシング協会日本フェザー級2位の現役選手。 トレーニングによって
体を鍛えると 心も強くなっていく。 大抵のことは乗り越えられ、 失敗してもクヨクヨせず、 すぐに気持ちを切り替えて 前に進んでいける。 心が強くなれば 人生の可能性も どんどん広がっていく。 ■ 谷村 新司 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35090037.html シンガーソングライター、タレント、作詞家、作曲家、大学教授。アリスのリーダー。 血液型はAB型。愛称はチンペイ。娘は歌手の谷村詩織。 大阪府河内長野市出身、大阪市東住吉区桑津育ち。 表彰歴には日本赤十字社金色有功章など。 自分で答えを出すしかない。
冷たいようですが、 気持ちが何かに頼っていると、 うまくいかなくなったとき、 絶対に誰かのせいにしてしまいます。 したがって、 自分の気持ちで アクションを起こすことが大事。 それが結果的に 自分らしく生きることにつながっていく。 ■ 中村 文昭 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35085811.html
三重県出身の実業家・講演家・ビジネス書作家。 クロフネカンパニー代表取締役を務める人物であり、 レストラン・ウェディング事業などを展開している他、講演家としても活躍。 また、農業と若者をつなげる「耕せ!にっぽん!」プロジェクトや 素敵な先生達にスポットを当てたイベント「あこがれ先生プロジェクト」なども プロデュースしている。 とにかく
「男は25歳までに肚をつくれ」と。 肚というのは、 本気でやるということ。 「自分は何のために生きていくのか」 という人生の着地点のような、 そういう揺るがないものを つくれということです。
|
|||||
この記事に