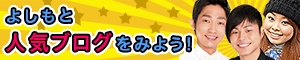■ 木戸 孝允 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35726742.html 武士(長州藩士)、政治家。 位階勲等は贈従一位勲一等。 明治維新の元勲であり、西郷隆盛、大久保利通と並んで「維新の三傑」と称される。 また維新の十傑の1人でもある。長州藩出身。 吉田松陰の教えを受け、藩内の尊王攘夷派(長州正義派)の中心人物となり、 留学希望・開国・破約攘夷の勤皇志士、長州藩の外交担当者、 藩庁政務座の最高責任者として活躍する。 特に志士時代には、幕府側から常時命を狙われていたにもかかわらず 果敢に京都で活動し続けた。 維新後、総裁局顧問専任として迎えられ、当初から「政体書」による 「官吏公選」などの諸施策を建言し続けていた。 文明開化を推進する一方で、版籍奉還・廃藩置県など封建的諸制度の解体に務め、 薩長土肥四巨頭による参議内閣制を整えた。 海外視察も行い、帰朝後は、かねてから建言していた憲法や 三権分立国家の早急な実施の必要性について政府内の理解を要求し、 他方では新たに国民教育や天皇教育の充実に務め、一層の士族授産を推進する。 長州藩主・毛利敬親や明治天皇から厚く信頼された。 しかし、急進派から守旧派までが絶え間なく権力闘争を繰り広げる 明治政府の中にあって、心身を害するほど精神的苦悩が絶えず、 西南戦争の半ば、出張中の京都で病気を発症して重篤となり、 夢うつつの中でも西郷隆盛を叱責するほどに政府と西郷双方の行く末を案じながら 息を引き取った。 その遺族は、華族令当初から侯爵に叙されたが、これは旧大名家、公家以外では、 大久保利通の遺族とともにただ二家のみであった。  偶 成 ( ぐ う せ い ) 木 戸 孝 允 偶 成 ( ぐ う せ い ) 木 戸 孝 允才 子 恃 才 愚 守 愚 少 年 才 子 不 如 愚 請 看 他 日 業 成 日 才 子 不 才 愚 不 愚 - 読 み 方 - 才子(さいし)は才を恃(たの)み愚(ぐ)は愚(ぐ)を守(まも)る 少年の才子 愚なるに如(し)かず 請(こ)ふ看(み)よ 他日(たじつ)業(ぎょう)成(な)るの日 才子は才ならず 愚は愚ならず - 意 訳 - 才気のあるものは己の才気を頼りにして、着実な努力をしようとしないが、 愚かで鈍いものは、自分の愚かを知り懸命に努力する。 少年時代の利口者は、愚かで鈍い者に及ばないことがある。 その証拠に、後日の成功の後を見るがよい。 少年時代の才子はもはや才子でなく、その当時の愚かで鈍い者が、 もはや愚かでなくなっていることを。 - 雑 感 -( e_dream21さん ) 維新三傑の一人の木戸孝允の作った七言絶句の漢詩です。 少年時代の桂小五郎は、ボーっとしていて、 無口で目立たない子供だったそうでした。 しかし、この平凡な少年は、ある人物との出会いによって、 人生が180度変わってしまいます。 その人物とは吉田松陰です。 己の愚かを知り、愚かだと言われてもその一日一日に全力を尽くすことこそ 正しい道という意味なんだと思います。 これからも向上心は失わずに努力して行かなくては・・。 日々修行です。(-_-;) ■ 「この素晴らしき世界」 (What a Wonderful World) ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35725034.html ルイ・アームストロング(Louis Armstrong)の歌唱で1968年にヒットした曲。 作詞・作曲は G・ダグラス(音楽プロデューサーのボブ・シールのペンネーム)と ジョージ・デヴィッド・ワイス。 ボブはベトナム戦争を嘆き、平和な世界を夢見て、この曲を書いたという。 1987年の映画『グッドモーニング, ベトナム』で、 戦時中のベトナムの牧歌的田園風景を映す印象的なシークエンスに BGMとして起用され、全米32位というリバイバルヒットとなった。 日本ではホンダ・シビック(3代目)や東海東京証券、東京海上日動火災保険、 ソニーなどのテレビコマーシャルに起用されたことがある。 What a Wonderful World I see trees of green, red roses too I see them bloom for me and you And I think to myself, what a wonderful world  木々は青々としげり 木々は青々としげりバラの花は赤く色づく 私やあなたのために咲く花たちを見ると しみじみ思うよ この世界はなんて素晴らしいんだろうと I see skies of blue and clouds of white The bright blessed day, the dark sacred night And I think to myself, what a wonderful world  青い空と真っ白な雲 青い空と真っ白な雲そして昼の輝きと夜の闇 しみじみ思うよ この世界はなんて素晴らしいんだろうと The colors of the rainbow, so pretty in the sky Are also on the faces of people going by I see friends shaking hands, saying how do you do They're really saying, I love you 空には七色の虹がかかる 過ぎ行く人たちの表情も美しい 友人たちは握手を交わしながら「ご機嫌よう」と言い 心から「大好きだよ」と言い合う I hear babies cry, I watch them grow They'll learn much more than I'll ever know And I think to myself, what a wonderful world Yes, I think to myself, what a wonderful world 赤ん坊が泣いてる この子たちが育つのを見ていよう 彼らはこれから先、私よりずっとたくさん学んでいくだろう しみじみ思うよ この世界はなんて素晴らしいんだろうと そう、本当に思うね なんて素晴らしいんだろう、この世界は - 雑 感 - ( e_dream21さん ) この曲をルイ・アームストロングが歌ったのは1967年の ベトナム戦争まっただ中の時代。 慈愛に満ちたその歌声には、 「争いなんかしなくても、思いやりあうだけで、 世界はこんなにも素晴らしいんだよ」 という彼のメッセージが込められていると言われています。 世界のいたる所で紛争が絶えません。 私には「思いやり」が有ると勝手に思い込んでいるだけなのでは? 日々修行です。(-_-;) ◇画像出典:George David Weiss ■ 松尾 芭蕉 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35723079.html 江戸時代前期の俳諧師。 蕉風と呼ばれる芸術性の極めて高い句風を確立し、 後世では俳聖として世界的にも知られる、日本史上最高の俳諧師の一人である。 芭蕉が弟子の河合曾良を伴い、元禄2年3月27日(1689年5月16日)に 江戸を立ち東北、北陸を巡り岐阜の大垣まで旅した紀行文『おくのほそ道』がある。  さまざまの こと思ひ出す 桜かな さまざまの こと思ひ出す 桜かな- 雑 感 - ( e_dream21さん ) 私も桜を見ると、あの日、あの時、あの人と見た桜を思い出してしまいます。 毎朝、ラジオ体操に行く城址公園で独り桜を見ていると、 本当に色々な事が蘇ってきます。 それと、年齢を重ねるごとに、散りゆく桜とわが人生を重ねて見てしまい・・。 新しい季節を彩る桜。 新たな目標に向かって気持ちを奮い立たせてくれる気がします。 もっと頑張らないと。日々修行です。(-_-;) ■ 一休 宗純 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35721410.html 室町時代の臨済宗大徳寺派の僧、詩人。 説話のモデルとしても知られる。 出生地は京都で、出自は後小松天皇の落胤とする説が有力視されている。 『一休和尚年譜』によると母は藤原氏、 南朝の高官の血筋であり、後小松天皇の寵愛を受けたが、 帝の命を狙っていると讒言されて宮中を追われ、 民間に入って一休を生んだという。 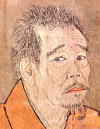 世の中は喰うて稼いで寝て起きて、 世の中は喰うて稼いで寝て起きて、さてその後は死ぬるばかりぞ - 雑 感 -( e_dream21さん ) 一休(1394-1481)の残した有名な道歌の一つです。 この道歌の解説を調べてみると、人間の一生のはかなさを表したものといえます。 人間の一生がこのようなものだと考えるならば、 あまりにも悲しいと言わなければなりませんし、よくよく考えると、 これ以上のものは何も無いと思います。 だから、ありのままを認めて生きていかなければなりません。と有りました。 私は何のために生きているのだろう?日々修行です。(-_-;) ■ 坂村 真民 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35719539.html 仏教詩人。 一遍の生き方に共感し、癒しの詩人と言われる。 愛媛県砥部町に「たんぽぽ堂」と称する居を構え、毎朝1時に起床し、 近くの重信川で未明の中祈りをささげるのが日課であった。 詩は解りやすい物が多く、小学生から財界人にまで愛された。 特に「念ずれば花ひらく」は多くの人に共感を呼び、その詩碑は全国、 さらに外国にまで建てられている。 森信三が早くからその才覚を見抜き後世まで残る逸材と評した。  尊いのは、 尊いのは、頭ではなく、手ではなく、 足の裏である。 一生人に知られず、 一生きたない処と接し、 黙々として、 その務めを果たしてゆく。 しんみんよ、 足の裏的な仕事をし、 足の裏的な人間になれ。 頭から光が出る。 まだまだだめ。 額から光が出る。 まだまだいかん。 足の裏から光が出る。 そのような方こそ、 本当に偉い人である。 ■ 安岡 正篤 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35717921.html 陽明学者・思想家。 多くの政治家や財界人の精神的指導者や御意見番として知られる人物であり、 安岡を師と仰いだ政治家には「吉田茂」「池田勇人」「佐藤栄作」「福田赳夫」 「大平正芳」など歴代の首相も名を連ねている。 「日本の黒幕」とも呼ばれた人物であるが、本人は 「自分はただの教育者にすぎない」と黒幕と呼ばれるのも嫌がっていたとのこと。 また「平成」の元号を考案者と言われており、 「いつか昭和が終わったら次は平成というのはどうだろう? 平和が成り立つという意味だ」と語ったとされている。  人間なにが悩みかというと、 人間なにが悩みかというと、自分が自分を知らざることである。 人を論じたり、 世を論じたりすることはやさしいが、 自分を論じ、 自分を知るということは、 実はこれが 一番大事であるにもかかわらず、 なかなか難しいことである。 人間は、先ず自分を責むべきであって、 世の中や時代を責むべきではない。 世の中が悪い、 時代が悪いというのならば、 そういう時世に対して、 一体自分はどれだけ役に立つのか、 それをどう解釈し、 それに対してどういう 信念・情熱を持っているのか、 よく自分を責めるがよい。 ◇参考記事:安岡正篤 ■ アラン(エミール=オーギュスト・シャルティエ) ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35716207.html ペンネームのアランは、フランス中世の詩人、 作家であるアラン・シャルティエ(英語版)に由来する。 1925年に著された『幸福論 (アラン)(フランス語版)』で名高いが、 哲学者や評論家としても活動し、アンリ・ベルクソンやポール・ヴァレリーと並んで 合理的ヒューマニズムの思想は20世紀前半フランスの思想に大きな影響を与えた。  人間には自分自身以外に、 人間には自分自身以外に、敵はほとんど いないものである。 最大の敵はつねに 自分自身である。 判断を誤ったり、 無駄な心配をしたり、 絶望したり、 意気消沈するような言葉を、 自分に聞かせたりすることによって、 最大の敵となるのだ。 ◇参考記事:お金持ちの知恵袋 ■ モハメド・アリ ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35714530.html アメリカ合衆国の元プロボクサー。 元世界ヘビー級チャンピオン。 アフリカ系アメリカ人であり、他にイングランドとアイルランドの血を引いていた。 1960年ローマオリンピックボクシングライトヘビー級金メダル獲得。 その後プロに転向し、ソニー・リストンを倒して世界ヘビー級王座を獲得。 ベトナム戦争の徴兵拒否や、 人種差別に関する発言、マルコム・Xとの関わりなど政治的言動から、 当時のアメリカの政権や保守派と対立し、ライセンス剥奪、試合禁止等、 たび重なる圧力を加えられたが、通算で3回のチャンピオン奪取に成功し、 通算19度の防衛を果たした。 ジョージ・フォアマンとザイールで対戦し、 8Rの一発で大逆転を演じたタイトルマッチや、 ジョー・フレージャーとの死闘など、数々の名勝負を残した。  不可能とは、 不可能とは、自らの力で世界を切り拓くことを放棄した臆病者の言葉だ。 不可能とは、 現状に甘んじるための言い訳に過ぎない。 不可能とは、 事実ですらなく、単なる先入観だ。 不可能とは、 誰かに決めつけられることではない。 不可能とは、 通過点だ。 不可能とは、 可能性だ。 - 原 文 - Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world they've been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact. It's an opinion. Impossible is not a declaration. It's a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is nothing. Muhammed Ali ■ 孔子「論語 巻第一 為政第二」 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35712825.html 春秋時代の中国の思想家、哲学者。儒家の始祖。 実力主義が横行し身分制秩序が解体されつつあった周末、 魯国に生まれ、周初への復古を理想として身分制秩序の再編と仁道政治を掲げた。 孔子の弟子たちは孔子の思想を奉じて教団を作り、戦国時代、 儒家となって諸子百家の一家をなした。 孔子と弟子たちの語録は『論語』にまとめられた。  子曰、吾十有五而志乎(干)学、 子曰、吾十有五而志乎(干)学、三十而立、四十而不惑、 五十而知天命、六十而耳順、 七十而従心所欲、不踰矩。 子曰わく、 吾十有五にして学に志す、 三十にして立つ、四十にして惑わず、 五十にして天命を知る、六十にして耳順がう、 七十にして心の欲する所に従って、矩を踰えず。 - 訳 - 先生が言われた。 「私は十五歳で学問に志し、 三十になって独立した立場を持って、 四十になってあれこれ迷わず、 五十になって天命をわきまえ、 六十になって人のことばが素直に聞かれ、 七十になると思うままに振舞ってそれでも道を外れないようになった。」 - 雑 感 -( e_dream21さん ) 私が小学生の時、時代劇の寺子屋みたいに日課として 祖父から論語を朗読させられ何十年もの月日が過ぎ去りました。 孔子が生まれたのは紀元前551年、いまから2550年前のこと、 孔子の教えは約2500年の間、無数の人々に影響を与えつづけてきたのですが、 堕落した怠惰な私は結果として、「論語読みの論語知らず」な 人生をおくっています。 「吾十有五にして学を志ざさず、三十にして立てず、四十にして迷い続け、 五十になっても天命を知らず、・・。」という有様です。 この言葉は数え年74歳まで生きた孔子が、晩年に自らの生涯を 振り返って述べたものだそうです。 どう努力したら孔子のような生き方ができるのでしょうか。 日々修行です。(-_-;) ■ 福沢 諭吉 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35711172.html 武士(中津藩士のち旗本)、蘭学者、著述家、啓蒙思想家、教育者。 慶應義塾の創設者であり、専修学校(後の専修大学)、 商法講習所(後の一橋大学)、伝染病研究所の創設にも尽力した。 他に東京学士会院(現在の日本学士院)初代会長を務めた。 そうした業績を元に明治六大教育家として列される。  人に交わるには 人に交わるには信を以てすべし。 おのれを信じて 人もまたおのれを信ず。 人々相信じて、 はじめて 自他の独立自尊を 実にするを得べし。 ◇参考関連記事:「明治」という国家 / 坂の上の雲マニアックス ◇参考関連記事:京都のお寺に育ったしばやんの歴史考察など ■ 西郷 隆盛 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35709404.html 武士(薩摩藩士)、軍人、政治家。 薩摩藩の盟友、大久保利通や長州藩の木戸孝允(桂小五郎)と並び、 「維新の三傑」と称される。 維新の十傑の1人でもある。 「西郷どん」とは「西郷殿」の鹿児島弁表現(現地での発音は「セゴドン」に近い) であり、目上の者に対する敬意だけでなく、親しみのニュアンスも込められている。 また「うどさぁ」と言う表現もあるが、 これは鹿児島弁で「偉大なる人」と言う意味である。 最敬意を表した呼び方は「南洲翁」である。 示 外 甥 政 直 外甥(がいせい)政直(まさなお)に示す
◇画像出典記事:敬天愛人一 貫 唯 唯 諾 一貫、唯唯(いい)の諾 従 来 鉄 石 肝 従来、鉄石(てっせき)の肝 貧 居 生 傑 士 貧居(ひんきょ)、傑士(けっし)を生み 勲 業 顕 多 難 勲業(くんぎょう)多難に顕(あら)わる 耐 雪 梅 花 麗 雪に耐えて梅花麗(うるわ)しく 経 霜 紅 葉 丹 霜を経て楓葉(ふうよう)丹(あか)し 如 能 識 天 意 如(も)し、能(よ)く、天意を識(し)らば、 豈 敢 自 謀 安 豈(あに)敢(あえ)て、自から安きを謀(はか)らむや。  - 解 釈 - - 解 釈 -引き受けたと心にちかったことは、 どこまでもただただひたむきにやり通さなければならない。 鉄の如く石の如く守ってきた胆力は、 いつまでもそれを変えてはならない。 豪傑の士というものは貧しい生活をしてきた人の中から現れ、 勲評価される事業というものは多くの困難を経て成し遂げられるのだ。 梅の花は雪に耐えて麗しく咲き、 楓の葉は霜を経て真赤に紅葉する。 もしこれらの天意が理解できたのなら、 安楽な生き方を選ぶことなどどうして出来ようか。 - 雑 感 -( e_dream21さん ) 「耐雪梅花麗」「ゆきにたえてばいかうるわし」と読みます。 冬の厳しい雪や寒さに耐えた梅の花が、 春になって一層美しく咲く様子を表しており、 人も試練を乗り越えてこそ大成するとの意味です。 1872年(明治5年)、西郷隆盛が妹の三男、市来政直のアメリカ留学に際して 贈った漢詩「偶成」の一節です。隆盛44歳の時。 私はどうしても楽な方へと向かってしまいます。 今は耐雪の時。日々修行です。(-_-;) ◇関連参考記事:ブログ・敬天愛人 ■ ジャン=ジャック・ルソー ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35707978.html ジュネーヴ共和国に生まれ、主にフランスで活躍した哲学者、政治哲学者。 一般的には政治哲学や社会思想の側面から語られることが多いが、 哲学や倫理学、人間学、自然学の他、音楽や音楽理論、文学や文学理論、 舞台芸術などの芸術分野など、幅広い関心を持ち、多方面で独自の思想を残している。 啓蒙思想の時代にあった18世紀フランスで活躍した。 ドゥニ・ディドロ、ジャン・ル・ロン・ダランベール、ヴォルテール等、 同時代の多くのフランスの知識人とともに百科全書派の一人に数えられる。  わたしたちは無知によって わたしたちは無知によって道に迷うことはない。 自分が 知っている事と 信じる事によって 道に迷うのだ。 ■ ポール・アーデン ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35706445.html 英国で様々な伝説を残している天才クリエイター。手掛けた広告はトヨタ、プリティッシュ、エアウェイズ、インターシティ、フジカラーなど数えきれない。「先を行く車はトヨタです」などのコピーで脚光を浴びた。2008年没。  これまでに聞いた これまでに聞いた最高のアドバイスは、 「驚かしてごらん」だ。 この言葉を心に刻んでしまうと、 もうどうやっても創造的に ならざるを得ない。 ■ ミハイ・チクセントミハイ ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35704698.html ハンガリー出身のアメリカの心理学者。 「幸福」、 「創造性」、 「主観的な幸福状態」、 「楽しみ」の研究(いわゆるポジティブ心理学)を行う。 著書『楽しみの社会学』でフローの概念を提唱したことで知られる。  どれだけ自分の意思を どれだけ自分の意思をコントロールできるかで 生活のクオリティが決まります。 ・
|
|||
この記事に