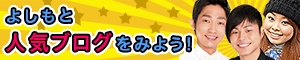■ 大棟 耕介 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35531399.html クラウン(道化師)。 筑波大学体育専門学群卒業後、名古屋鉄道株式会社に入社。 同社に勤務しながらクラウン(道化)の勉強をはじめ、 クラウン集団「プレジャーB」を結成。 その後プロに転身し、遊園地やアミューズメントパーク、サーカス、 小学校などでパフォーマンスを行う。 また、2004年頃から病院を訪問して 闘病中の子どもたちをケアする「ホスピタルクラウン」活動を開始。 2008年にWCA(World Clown Association)金メダルを受賞。  一生懸命やれば、 一生懸命やれば、どんな仕事も 天職になるんじゃないかな。 一生懸命やれば、 どんな仕事だって 楽しくなると思う。 もし仕事がつまらないのだとしたら、  それは一生懸命やってないから。 やらされてやっていても、 つまらないでしょ。 前のめりにやれば、 どんなことでも 面白くなっていくんです。 http://www.rctoyota.ac.jp/2009/05/post-27.html ■ 遠藤 周作 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35529944.html 小説家。随筆や文芸評論や戯曲も手がけた。 父親の仕事の都合で幼少時代を満洲で過ごした。 帰国後の12歳の時に伯母の影響でカトリックの洗礼を受けた。 1941年上智大学予科入学、在学中同人雑誌「上智」第1号に 評論「形而上的神、宗教的神」を発表した(1942年同学中退)。 慶應義塾大学文学部仏文科を卒業後、1950年にフランスへ留学。 帰国後は批評家として活動するが、1955年半ばに発表した小説「白い人」が 芥川賞を受賞し、小説家として脚光を得た。 第三の新人の一人。 キリスト教を主題にした作品を多く執筆し、 代表作に『海と毒薬』『沈黙』『侍』『深い河』などがある。 1960年代初頭に大病を患い、その療養のため町田市玉川学園に転居してからは 「狐狸庵山人(こりあんさんじん)」の雅号を名乗り、 ぐうたらを軸にしたユーモアに富むエッセイも多く手掛けた。  人間らしく生きるためには 人間らしく生きるためには七分は真面目人間 三分は不真面目人間で生活するのが 「生きる知恵」というべきであろう。 ◇参考記事 (有隣堂・座談会) http://www.yurindo.co.jp/static/yurin/back/yurin_460/yurin2.html ◇参考記事 (今日の出来事ロジー) http://blogs.yahoo.co.jp/sw21akira/44803177.html ◇参考記事 (遠藤周作名言bot) https://twitter.com/enshu_bot ■ 小田嶋 隆 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35528590.html コラムニスト、テクニカルライター。 大学卒業後には味の素ゼネラルフーヅに就職したが、 入社翌年の1981年(昭和56年)には退職し、小学校事務員見習い、 ラジオ局AD(アシスタントディレクター)、ロックバンド座付き作詞家などを経て、 テクニカルライターとなった。 1988年(昭和63年)、コンピュータに関連する事項を軽妙に描いた コラム集 『我が心はICにあらず』以降はコンピュータ関係にとどまらず、 様々な事物を辛口に論じるコラムニストとなった。  仮にもう一回 生まれるのだとしても、 お前はお前だと思うぞ。 煩悩の性質からして。 http://www.sekigaku-agora.net/course/odajima_takashi.html ■ 大原 千鶴 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35526871.html 料理研究家。京都・花背の名料亭で生まれ育ち、 小学生の頃には店のまかないを担当するなど、料理の心得を学ぶ。 現在は3人の子どもを育てながら、雑誌等でつくりやすい家庭料理を提案している。  真面目に一生懸命 真面目に一生懸命より良く生きようと思うからこそ 心って モヤモヤするんです。 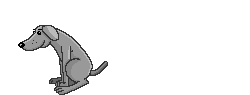 そう思うと モヤモヤする人って 素敵なのかもしれません。 http://family-first.jp/lifestyle/017/page03.html ■ 西郷 隆盛 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35525213.html 武士(薩摩藩士)、軍人、政治家。 薩摩藩の盟友、大久保利通や長州藩の木戸孝允(桂小五郎)と並び、 「維新の三傑」と称される。維新の十傑の1人でもある。 「西郷どん」とは「西郷殿」の鹿児島弁表現(現地での発音は 「セゴドン」に近い)であり、目上の者に対する敬意だけでなく、 親しみのニュアンスも込められている。 また「うどさぁ」と言う表現もあるが、 これは鹿児島弁で「偉大なる人」と言う意味である。 最敬意を表した呼び方は「南洲翁」である。  己を尽くして人を咎めず。 己を尽くして人を咎めず。我が誠の足らざるを常にたずぬるべし。 我を愛する心を以って人を愛せ。 自己を許すが如く人を許せ。 人を責めるが如く自己を責めよ。 http://www.kirei-ni.com/portrait/shouzouga/gallery-12.html ◇関連記事 (写真を見ながらキャンバスに一筆一筆描く油絵の肖像画!) http://www.kirei-ni.com/ ■ 吉屋 信子 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35523248.html 1920年代から1970年代前半にかけて活躍した小説家。 栃木高等女学校(現栃木県立栃木女子高等学校)に入学した際、 新渡戸稲造の「良妻賢母となるよりも、まず一人のよい人間とならなければ困る。 教育とはまずよき人間になるために学ぶことです。」 という演説に感銘を受け、そのころから少女雑誌に短歌や物語の投稿をはじめる。 日光小学校の代用教員になるが、文学への道を捨てがたく、 卒業後に上京して作家を志し、1916年(大正5年)から『少女画報』誌に連載した 『花物語』で人気作家となる。 その後、『大阪朝日新聞』の懸賞小説に当選した『地の果まで』で 小説家としてデビュー、徳田秋声らの知遇を得る。)  不幸は 不幸は突然くるかも知れぬが、 幸福は 突然はやって来ない。 http://matome.naver.jp/odai/2135773198139189401/2135787961260078103 ■ 宮田 珠己 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35522032.html 旅行エッセイスト。兵庫県生まれ。大阪大学工学部土木工学科卒。 卒業後、株式会社リクルートに就職し、不動産関係の部門に配属される。 のち、編集部門に転属。愛称はタマキング。 1995年新風舎より処女作『旅の理不尽』を自費出版、会社を退職。 以後、アジア地域を中心に旅し、旅行記・エッセイを刊行する。 最近は国内紀行が主になってきている。  頑張った自分にご褒美とか言って、 頑張った自分にご褒美とか言って、小さな満足で ごまかしている人がいるが、 簡単にできる楽しみを 重ねていっても、 決して充実感なんて得られない。 充実感は、もっと 根っこの部分から来るもので、 自分の本質を揺るがすような、 ヒリヒリした 危なかっしさと背中合わせの、 リスクを伴うものだと思う。 つまり、冒険なのだ。 冒険しているときこそ、 毎日が充実するのである。 http://www.ceres.dti.ne.jp/~m-goto/miyata.main.html ■ 池波 正太郎 ◇出典 http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/35520516.html 小説『真田太平記 五』より 戦後を代表する時代小説・歴史小説作家。 『鬼平犯科帳』『剣客商売』『仕掛人・藤枝梅安』『真田太平記』など、 戦国・江戸時代を舞台にした時代小説を次々に発表する傍ら、 美食家・映画評論家としても著名であった。  すべてがわかったような すべてがわかったようなつもりでいても、 双方のおもいちがいは 間々あることで、 大形にいうならば、 人の世の大半は、 人びとの勘ちがいによって 成り立っている といってもよいほどなのだ。 http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201007190119.html |
|||
この記事に