とても有名な句。 や、かな、けりが代表する切れ字は 俳句の代表的語法である。 波郷の句、末尾の「けり」が切れ字だが、 その切れ字は、霜柱の立てる 微妙、繊細な音に匹敵する、 というのだ。 ちなみに、私のパソコンで 「きれじ」を漢字に変換しようとすると まず「切れ痔」が出る。 おかしい。 |
|||||||
この記事に
こんにちは、ゲストさん
![]() 過去の投稿月別表示
過去の投稿月別表示
詳細
例えば、空間にばらまかれた文字のかたまりの場合、 前後が代わっても何の違和感もありません。 こんな場合は平行視でも、交差視でもどちらでも見られます。 従って、視差のある画像を交合に配置するだけで 立体空間を感じることができます。 この場合は、平行視でも、交差視でも 立体感を感知できます。 ただし、文字の位置関係は、平行視と交差視で奥行き感が逆転します。 以下に参考画像を表示します。
 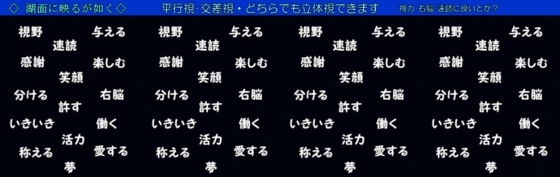 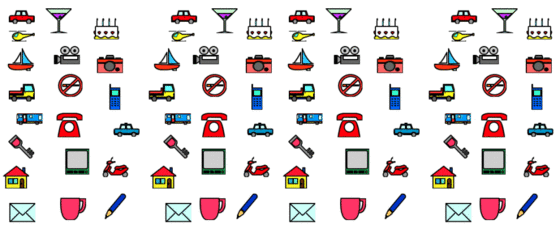  、
|
|||||||||||
この記事に

今日 | 全体 | |
|---|---|---|
| 21 | 168503 | |
| 0 | 59 | |
| 0 | 2928 | |
| 0 | 126 |