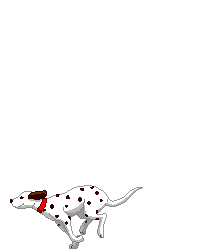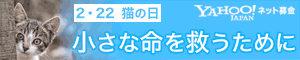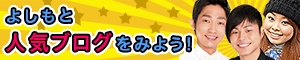偉人の名言集【101】■ 成毛 眞 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34009772.html1979年中央大学商学部卒業。 自動車部品メーカー、アスキーなどを経て 1986年にマイクロソフト株式会社(日本法人、以下MSKK)入社。 1991年よりMSKK代表取締役社長。 2000年に退社後、同年5月に投資コンサルティング会社「インスパイア」を設立。 事業内容は、上場企業にコンサルティングを行い、 業績が上がることで株価上昇のキャピタルゲインを得る成果報酬型コンサルティング事業。 現在、スルガ銀行株式会社、株式会社スクウェア・エニックスの社外取締役や、 様々なベンチャー企業の取締役・顧問などを兼職。早稲田大学客員教授も務める。 2009年に逮捕された村木厚子・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長について、 「無実の村木厚子さんの解放を求めます」との声明を発表した。 どういうわけか日本では、我慢を美徳として考える傾向がある。
そして、強い自制心を持つことが大人の証明になるとされる。 しかし、私の周囲の成功者とされる人に、我慢強い人物は見当たらない。 逆に、やりたいことがまったく我慢できない、子供のような人ばかりだ。 そういう人は、好きでやっているのだから、時間を忘れていくらでも頑張るし、 新しいアイデアも出てくる。 我慢をして嫌々ながらやっている人が、こういう人達に勝てるはずがないではないか。 ■ 坂村 真民 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34007830.html 仏教詩人。 詩は解りやすい物が多く、小学生から財界人にまで愛された。 特に「念ずれば花ひらく」は多くの人に共感を呼び、 その詩碑は全国、さらに外国にまで建てられている。 森信三が早くからその才覚を見抜き後世まで残る逸材と評した。 人間いつかは終わりがくる。
前進しながら終わるのだ。 ■ 古島 一雄 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34006141.html 明治、大正、昭和前期の日本のジャーナリスト、衆議院議員、貴族院議員。 日本新聞の記者となり、日清戦争では、同僚であった正岡子規と従軍し戦況を報道した。 他人の中傷に対して、
どこまで弁解せずにおられるか、 これを試してみるのも、 人間修練の一方法である。 ■ 司馬 遼太郎 ◇ http://blogs.yahoo.co.jp/e_dream21/34004062.html
小説家、ノンフィクション作家、評論家。 筆名の由来は「司馬遷に遼(はるか)に及ばざる日本の者(故に太郎)」から来ている。 産経新聞社記者として在職中に、『梟の城』で直木賞を受賞。 歴史小説に新風を送る。 代表作に『竜馬がゆく』『燃えよ剣』『国盗り物語』『坂の上の雲』など多くがあり、 戦国・幕末・明治を扱った作品が多い。 PS 「二十一世紀に生きる君たちへ」は、 1996年に亡くなられた司馬 遼太郎さんが、 21世紀に生きる子供向けに書かれた随筆です。 やがて21世紀を担っていくであろう子供たちに向けての 力強いメッセージと羨望の念が込められているこの文章は考えさせられる事が多くあります。 子供達が自殺しない世の中になって欲しいと切望します。 私は歴史小説を書いてきた。
もともと歴史が好きなのである。 両親を愛するようにして、歴史を愛している。 歴史とは何でしょう、と聞かれるとき、 「それは、大きな世界です。 かつて存在した何億という人生がそこにつめこまれている世界なのです。」 と、答えることにしている。 私には、幸い、この世にたくさんのすばらしい友人がいる。 歴史の中にもいる。 そこには、この世では求めがたいほどにすばらしい人たちがいて、 私の日常を、はげましたり、なぐさめたりしてくれているのである。 だから、私は少なくとも2千年以上の時間の中を、生きているようなものだと思っている。 この楽しさは、───もし君たちさえそう望むなら───おすそ分けしてあげたいほどである。 ただ、さびしく思うことがある。 私が持っていなくて、君たちだけが持っている大きなものがある。 未来というものである。 私の人生は、すでに持ち時間が少ない。 例えば、21世紀というものを見ることができないに違いない。 君たちは、ちがう。 21世紀をたっぷり見ることができるばかりか、そのかがやかしいにない手でもある。 もし「未来」という町角で、私が君たちをよびとめることができたら、どんなにいいだろう。 「田中君、ちょっとうかがいますが、あなたが今歩いている21世紀とは、どんな世の中でしょう。」 そのように質問して、君たちに教えてもらいたいのだが、ただ残念にも、 その「未来」という町角には、私はもういない。 だから、君たちと話ができるのは、今のうちだということである。 もっとも、私には21世紀のことなど、とても予測できない。 ただ、私に言えることがある。それは、歴史から学んだ人間の生き方の基本的なことどもである。 昔も今も、また未来においても変わらないことがある。 そこに空気と水、それに土などという自然があって、 人間や他の動植物、さらには微生物にいたるまでが、 それに依存しつつ生きているということである。 自然こそ不変の価値なのである。 なぜならば、人間は空気を吸うことなく生きることができないし、 水分をとることがなければ、かわいて死んでしまう。 さて、自然という「不変のもの」を基準に置いて、人間のことを考えてみたい。 人間は───繰り返すようだが───自然によって生かされてきた。 古代でも中世でも自然こそ神々であるとした。 このことは、少しも誤っていないのである。 歴史の中の人々は、自然をおそれ、その力をあがめ、 自分たちの上にあるものとして身をつつしんできた。 この態度は、近代や現代に入って少しゆらいだ。 ───人間こそ、いちばんえらい存在だ。 という、思い上がった考えが頭をもたげた。 20世紀という現代は、ある意味では、自然へのおそれがうすくなった時代といってもいい。 同時に、人間は決しておろかではない。 思いあがるということとはおよそ逆のことも、あわせ考えた。 つまり、私ども人間とは自然の一部にすぎない、というすなおな考えである。 このことは、古代の賢者も考えたし、また19世紀の医学もそのように考えた。 ある意味では、平凡な事実にすぎないこのことを、20世紀の科学は、 科学の事実として、人々の前にくりひろげてみせた。 20世紀末の人間たちは、このことを知ることによって、 古代や中世に神をおそれたように、再び自然をおそれるようになった。 おそらく、自然に対しいばりかえっていた時代は、 21世紀に近づくにつれて、終わっていくにちがいない。 「人間は自分で生きているのではなく、大きな存在によって生かされている。」 と、中世の人々は、ヨーロッパにおいても東洋においても、そのようにへりくだって考えていた。 この考えは、近代に入ってゆらいだとはいえ、右に述べたように近ごろ再び、 人間たちはこのよき思想を取りもどしつつあるように思われる。 この自然へのすなおな態度こそ、21世紀への希望であり、君たちへの期待でもある。 そういうすなおさを君たちが持ち、その気分をひろめてほしいのである。 そうなれば、21世紀の人間はよりいっそう自然を尊敬することになるだろう。 そして、自然の一部である人間どうしについても、 前世紀にもまして尊敬しあうようになるのにちがいない。 そのようになることが、君たちへの私の期待でもある。 さて、君たち自身のことである。 君たちは、いつの時代でもそうであったように、自己を確立せねばならない。 ───自分に厳しく、相手にはやさしく。 という自己を。 そして、すなおでかしこい自己を。 21世紀においては、特にそのことが重要である。 21世紀にあっては、科学と技術がもっと発達するだろう。 科学・技術がこう水のように人間をのみこんでしまってはならない。 川の水を正しく流すように、君たちのしっかりした自己が科学と技術を支配し、 よい方向に持っていってほしいのである。 右において、私は「自己」ということをしきりに言った。 自己といっても、自己中心におちいってはならない。 人間は、助け合って生きているのである。 私は、人という文字を見るとき、しばしば感動する。 斜めの画がたがいに支え合って、構成されているのである。 そのことでも分かるように、人間は、社会をつくって生きている。 社会とは、支え合う仕組みということである。 原始時代の社会は小さかった。 家族を中心とした社会だった。 それがしだいに大きな社会になり。 今は、国家と世界という社会をつくりたがいに助け合いながら生きているのである。 自然物としての人間は、決して孤立して生きられるようにはつくられていない。 このため、助けあう、ということが、人間にとって、大きな道徳になっている。 助け合うという気持ちや行動のもとのもとは、いたわりという感情である。 他人の痛みを感じることと言ってもいい。 やさしさと言いかえてもいい。 「いたわり」 「他人の痛みを感じること」 「やさしさ」 みな似たような言葉である。 この三つの言葉は、もともと一つの根から出ているのである。 根といっても、本能ではない。 だから、私たちは訓練をしてそれを身につけねばならないのである。 その訓練とは、簡単なことである。 例えば、友達がころぶ。 ああ痛かったろうな、と感じる気持ちを、その都度自分中でつくりあげていきさえすればいい。 この根っこの感情が、自己の中でしっかり根づいていけば、 他民族へのいたわりという気持ちもわき出てくる。 君たちさえ、そういう自己をつくっていけば、 二十一世紀は人類が仲よしで暮らせる時代になるのにちがいない。 鎌倉時代の武士たちは、 「たのもしさ」 ということを、たいせつにしてきた。 人間は、いつの時代でもたのもしい人格を持たねばならない。 人間というのは、男女とも、たのもしくない人格にみりょくを感じないのである。 もう一度くり返そう。 さきに私は自己を確立せよ、と言った。自分に厳しく、相手にはやさしく、とも言った。 いたわりという言葉も使った。 それらを訓練せよ、とも言った。それらを訓練することで、自己が確立されていくのである。 そして、“たのもしい君たち”になっていくのである。 以上のことは、いつの時代になっても、人間が生きていくうえで、 欠かすことができない心がまえというものである。 君たち。 君たちはつねに晴れあがった空のように、たかだかとした心を持たねばならない。 同時に、ずっしりとたくましい足どりで、大地をふみしめつつ歩かねばならない。 私は、君たちの心の中の最も美しいものを見続けながら、以上のことを書いた。 書き終わって、君たちの未来が、 真夏の太陽のようにかがやいているように感じた。 |
この記事に